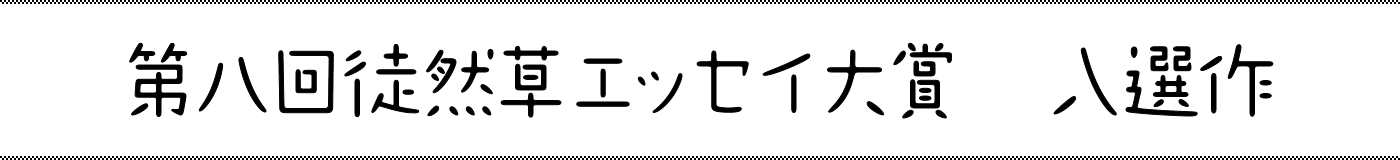
満天の星空。今にも落ちてきそうなほど眩しく輝く星々。多くの人は、そんな美しいものを夢中で眺めるのだろう。しかし、私は違った。私は、暗い夜空の中でただ一人ぽつんと今にも消えそうなほど薄く光る小さな小さな星が好きだ。
それを好きになった始まりはいつなのか。それは、私が八歳のころの話だ。私には、大好きな親戚のおばちゃんがいた。そのおばちゃんは、手先が器用でとても物静かな人だった。親戚一同で集まってワイワイと騒いでいた時も、私が彼女から教わった新しいあやとりの技を覚えて自慢げに披露していた時も、抱っこをせがんだ時でも、会ったときはいつでも私の大好きな優しいにこにこ笑顔を浮かべて隣にちょこんと座ってくれる、そんなおばちゃんだった。隣にいてくれたら落ち着くし、私は彼女のことが本当に本当に大好きだった。なので、帰ってしまいそうになると胸が苦しくなるほど悲しくなって、よく手も付けられない癇癪を起こしたものだ。そのたびに、手先が器用なおばちゃんは、ビーズをピアノ線で編んだブレスレットを作って渡してくれて、私の癇癪が収まるまでずっとそばにいてくれた。そして、おばちゃんは去り際にいつもこう言っていた。
「寂しくなったらいつでも私を思い出してね」
と。この時はとても幸せで、いつかこの幸せが崩れてしまうことなんて私は露ほど思っていなかった。
最後に会ったときから約一年後の秋のある日だった、おばちゃんが亡くなったのは。亡くなった、という知らせを母から聞いたときは心にぽかんと穴が開くような感覚だった。自分の身近でおきた初めての死だからか、大好きなおばちゃんが亡くなったという事実を受け入れることが出来なかったか、はたまたその両方か。理由は分からないが、泣くことも何も出来ずにただ椅子に座っていた。
数日後に参加したお葬式のことはほとんど何も覚えていない。けれど、そのあとに見た星空のことなら今でもとても鮮明に覚えている。あの日の空は、久しぶりに満開の星空になっていた。きらきらと圧倒的な光を放って輝くそれらの星々の中に、どの星よりも小さく、でも、どの星よりもやわらかに包み込むような光を出して光る星を見つけた。その瞬間、涙がほろりと私の頬をつたった。ああ、おばちゃんはここにいたんだ。私の大好きなおばちゃんはここにいたんだ。そう思うと、私の心にぽかんと空いていた穴に一気に感情が押し寄せ、涙の泉をつくった。とめどなく押し寄せる涙の渦を感じながら揺れる瞳でその星を見たら、その星は、“私のことを思い出してくれたかな、私はいつでもあなたのそばにいるよ”と言っているようだった。
私の記憶にある星空の始まりは、ワクワクしたりするものではなかった。でも、私にとってはとても大切な宝物だ。
今日も星空を見上げる。あ、あの星だ。おばちゃん、私は元気だよ。