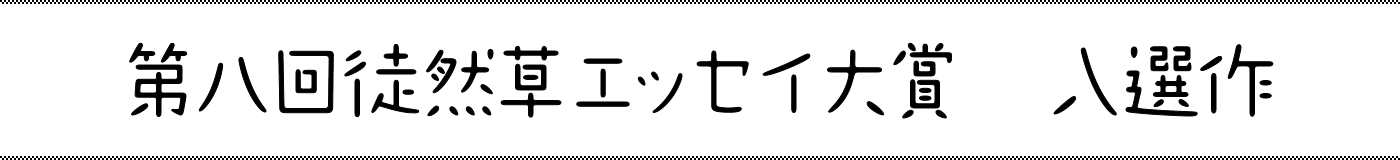
夕焼けと夜の暗さが入り混じった空に、無数の羽音とさえずりが響き渡る。手を伸ばせばすぐ届きそうな高さで飛んでいるのは、数えきれないほどのツバメ達だ。大空を埋め尽くさんばかりに飛び交う翼を見ながら、僕ははじまりの時を思い出していた。
小学一年のとき、国語の教科書で『くちばし』という話を読んだことが、今に続く僕と野鳥との出会いだ。調べ学習で鳥の図鑑を手に取った僕は、空を自由に飛び回る野鳥にひかれ、野鳥観察の第一歩を踏み出した。そして、小学三年の夏休みに母の郷里である大阪に帰省した際、ツバメのねぐら入り観察会という催しを見つけて参加したことが、その後の僕に大きな影響を与えることになる。
ツバメは、日本のはるか遠く、東南アジア等から約四千キロもの距離を飛んで、春に日本へ渡ってくる。その後夏にかけて人家の軒先などで子育てをし、秋になるとまた南方へ渡るというサイクルで過ごしているのだが、夏の終わり頃、巣立った幼鳥や親鳥達が河川敷やため池のヨシ原に集団でねぐらを作り、そこで早朝まで休む習性がある。ねぐら入りは、夕暮れどきに何万羽ものツバメ達が一斉にヨシ原に舞い降りる姿を観察できる、夏限定の一大ショーなのだ。
淀川の鵜殿で頭上を飛び交う約三万羽ものツバメの姿を初めて目にした僕は、その光景に圧倒されて言葉もなくただ見入っていた。ねぐらの葦に降りたツバメ達はしばらくおしゃべりをするかのように鳴いているが、徐々に静かになっていく。その様子とは逆に、僕の心は高鳴っていた。もっと野鳥達を見てみたい、深く知りたい。
そんな僕に、会のリーダーが声をかけてくれた。ツバメに限らず色んな野鳥が実は身近に街で見られること、図鑑の見方、探鳥のコツなど、幼い僕に分かるように優しく手ほどきをしてくれたのだ。僕とは七十歳以上も離れた彼との交流が始まった瞬間だった。この鳥見の師匠は、以来折にふれて定点観察の報告をし合ったり、時には二人で探鳥をする、僕の野鳥の知識を深める上でかけがえのない人となった。
そして今年の夏、僕は奈良県の平城宮跡での観察会に参加した。ここは約六万羽ものツバメが集まる、全国でも有数のねぐら入りの場所だ。夕闇が迫ると徐々にツバメ達が高い空に集まり始めた。日没とともに、ツバメ達の高度が下がり、数も増していく。やがて、無数の翼が僕の頭上からヨシ原めがけて降下を始めた。何万羽もの群れが何度も旋回しては一斉に降りるその光景は、まさに圧巻だ。ツバメ達に囲まれながら、僕は改めてはじまりの時に感謝した。僕も本格的に野鳥の世界に導いてくれたツバメ達と、そしてリーダーとの出会いは、僕の人生に新たな扉を開いてくれた。これからもたくさんのはじまりを経験し、積み重ねながら、僕と野鳥との世界は続いていくのだろう。
夕景のツバメ達は、いつも僕の心に舞っている。