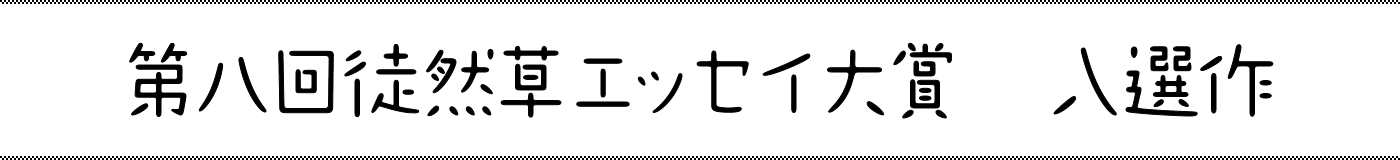
教師になってはや十四年。今まで多くの生徒との出会いがあり、その一つひとつが私にとってかけがえのない財産となっている。なかでも、自分自身の甘さに気づかせてくれたある生徒の存在は、私の励みとなっている。
大学卒業後、私は念願叶って高校の英語教師となった。当時私の周りでは教員になることを第一志望に考えている人は少なく、教員免許は取得しても一般企業に就職する人がほとんどだった。私も教師の大変さについては知ったつもりでいたが、「だからこそやりがいがあるのだ」と意気込み、他の一般企業には目もくれず、教職の道を選んだ。
私が教師を志したのは、中学生の時に読んだ小説『二十四の瞳』がきっかけだった。素直な子供たちに慕われ、逆境にもめげずに自分の信念を貫く姿に憧れ、私の理想の教師像となった。目を輝かせて自分を見つめる子供たちに、熱く人生訓を語る私――。いつしかそんなイメージが私の中で膨らんでいったのだ。
ところが、私が最初に赴任した学校は、そんなイメージとはかけ離れた所だった。そこは、全日制の高校を退学してきた生徒や、いじめ・不登校・非行といった問題を抱えた生徒が多く通うサポート校だったのだ。まともに勉強したことがなく、家族や友人と健全な人間関係を築いたこともない彼らが、人との付き合い方や礼儀など知るはずもない。新学期初日、ゴミが散乱する教室で私に向けられたのは、きらきら輝く瞳ではなく、すべてを拒絶するようにこちらを睨みつける、希望を失った目であった。あれほど準備して臨んだ授業だったが、教科書を開いている生徒はごく僅か。授業中の私語や飲食は日常茶飯事で、ひどいクラスでは化粧をしたり携帯ゲームに夢中になったりと、やりたい放題の無法地帯だった。恐る恐る注意をすれば、無視されるか「ウザイ」「新人のくせに」と憎まれ口を叩かれる。自作のプリントを配れば、私の努力はたちまち紙ヒコーキとなって教室中を飛び交い、授業後にはくしゃくしゃに丸められて教室の隅に捨てられていた。
正真正銘の授業崩壊を目の当たりにし、私の理想の教師像は早くも音を立てて崩れていった。同期の仲間たちも「やってられない」「割に合わない」と言って、一人、また一人と辞めていった。「学ぶ楽しさを教えたい」と思って教師になった私だったが、教室へ向かう足取りは日に日に重くなり、授業中はただ早く時が過ぎることだけを祈って、時計ばかり気にするようになった。こうして理想と現実の隔たりに悩まされるうち、当初は持っていた教職への情熱も消えかかっていた。
そんな状況が半年ほど続き、我慢の限界を感じ始めた私は、辞職を考えるようになった。そしてついに辞表を提出する決意したその日、私は午後の授業を終え、いつものように逃げるようにして教室を出ていった。「これからはもうこんな惨めな思いをしなくて済むのだ」と、内心晴れ晴れとした気分で職員室へ戻ろうとしたその時、「先生!」と、一人の女子生徒が駆け寄ってきた。自分のことを「先生」と呼んでくれるのは彼女だけだったので、よく印象に残っている生徒だった。その子が突然、「これ、読んで下さい」と言って一枚のメモ用紙を私に手渡したのだ。読んでみると、それは私への手紙だった。そこには、「いつもクラスが騒がしく、先生に迷惑をかけてすみません。でも私は、そんな状況でも一生懸命に教えようとしてくれている先生の姿に、いつも元気を貰っています。だからこれからも、先生らしく頑張って下さい」と書かれていた。
半ば投げやりになっていた自分の姿が、そんなふうに映っていたなんて……。私は驚きと感動で胸が一杯になり、その場で何度も手紙を読み返した。拙い私の話も、真剣に聞こうとしてくれている生徒がいた。けれども、私はそんな生徒の存在にはまるで気づかず、気づこうともしていなかったのだ。手紙を貰った嬉しさと同時に、反省の念が込み上げた。思えば私は、目の前の生徒のことよりも自分への関心ばかりが濃くなり、現状を変えるための努力を怠っていた。「報われない」と思うのは、事実報われる資格のない自分であることに他ならなかったのだ。私は持っていた辞表を破り捨てた。「不格好でも衝突してもいい。もう一度正面から生徒と向き合ってみよう」と決意したのだ。本当の意味で、教師としての第一歩を踏み出した瞬間だった。
あれから約十年。手紙をくれたあの生徒のおかげで、私は今も教師を続けている。今後も、あらゆる差別や偏見、無知無関心を敵に回し、闘う日々が続くだろう。だが私には、出会った人との縁を生かしていく使命がある。教師として初心を思い出させてくれるあの手紙は、私の心強いお守りだ。これからも教員人生の第一ボタンとして、私を支えてくれるだろう。