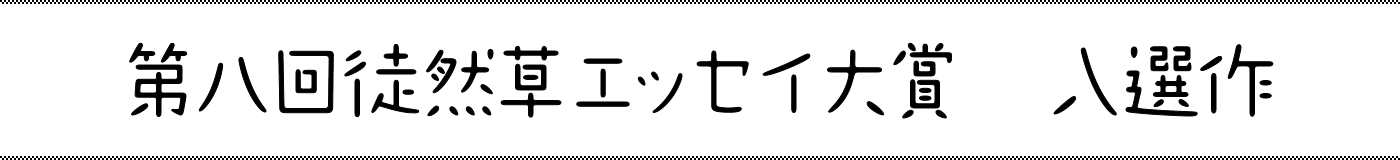
それがすべての始まりだった。
10年ほど前、まだ小学校の校長をしていた頃のことだ。「なわとび月間」と呼ばれる取り組みの中で、学校中がなわとびに熱くなっていた。
その日、昼休みの校庭で、私は何人かのなわとび自慢の子供たちの輪の中にいた。1年生から6年生まで、それぞれの学年の目標をクリアした者たちだけが、学年に関係なくチャレンジできる種目がある。それが、なわとび二重跳びの連続回数を競う、校長への挑戦だ。体育好きの校長として、私が勝手に発案したものだ。だから、そう簡単に負ける訳にはいかない。20回や30回は当たり前に跳んで、そこから先が本当の勝負になる。そして校長に勝った者は、「なわとび名人」の称号を手にすることになる。応援のギャラリーも大勢集まり、私も気合が乗ってきた。
一斉にスタートを切った。それぞれ跳ぶリズムが違うので、体育委員会の6年生が一人ずつついて数えてくれる。さすがになわとび自慢ばかりだ、誰もミスする者はいない。私も順調に、5回、10回と跳び続ける。いや、順調ではなかった。15回の頃にはなぜか急に苦しくなり、意地で何とか20回を超えたものの、そこで私は自ら跳ぶのをやめた。
子供たちの大きな失望のため息が私を包んだ。
「あ~あ、やっぱりおじいちゃんだからね」
そんな声も聞こえた。
どうもおかしい。なわとびには、私も自信があった。小学生の時には、二重跳びのクラスチャンピオンになって、さらに難しいはやぶさ跳びや、三重跳びにも挑戦していったものだ。
子供たちの帰った後、校庭の隅で、何度も二重跳びを試してみた。やはり跳べなくなっている。若い頃は50回など平気で跳んでいたのだ。スタミナにも問題があるのかもしれないが、跳んでいるうちに、タイミングが少しずつずれていくのが分かる。まるで跳び方を、忘れてしまったかのようだ。私の心の中に、黒い雲が広がっていった。
確かに子供たちから見れば、年寄りかもしれない。だが、まだ50代だった。老け込むには早い。しかし悲劇は、まだ続いた。
なわとびショックのすぐ後に、毎年プライベートで参加している、市の10㎞ロードレース大会があった。あくまでマイペースでの完走を目指すものだが、やはり走る以上は、毎年自己ベストをねらっていた。ところが今回は、前年より一気に10分間以上もタイムが悪くなってしまった。沿道で応援してくれていた知人から、「何だか死にそうな顔で走っていたぞ」と言われたほどだ。
自分では分からないが、普段の歩き方がおかしいと言う人もいる。時々手も震える。テレビのコマーシャルでやっているサプリメントもいろいろ試してみたが、改善されない。仕方なく、病院へ行った。
パーキンソン病だった。
毎週月曜日の朝会で壇上に立つと、全身が小刻みに震えるようになった。全校児童が、教職員がそれを見ている。休み時間にも、校長室から出ないことが多くなった。少しずつ、しかし確実に動かなくなっていく自分の体に、私は怯えた。
パーキンソン病は、今の医学では治療方法のない難病だ。多くの場合服薬とリハビリで現状を維持するか、病気の進行を遅らせることしかできない。私は比較的若くしての発症だったため、その分進行は早かった。
60歳の定年退職まで、あと2年半。校長職という責任ある立場を全うできるだろうか。私は早期退職を考えた。しかし周囲が許してくれなかった。
できないことは周りで手を貸す。ただしできることから逃げるな。病気に負けずに一所懸命生きていく姿を、子供たちに見せることこそが教育ではないのか。そんな叱咤激励に応えない訳にはいかない。校長室のデスクの引き出しにしまったままの愛用のなわとびを、時折握りしめながら、前だけを見て歩いた。そして何とか、定年退職まで勤め上げることができたのだった。
完治することがないということは、つまり「死ぬまで病気と付き合う」という意味でもある。遠い道だ。振り返れば、もうすぐ10年になる。
今私は、歩くのにも杖を手放すことができず、遠出の時は車椅子に頼る。毎朝ジョギングで走った土手で、風とかけっこしてみることも、もうない。やらなくなったもの、できなくなったものはいくらでもある。
しかし、ひとつだけもう一度挑戦してみたいものがある。なわとびだ。二重跳びなどでなくてもいい。たった1回でもいい。10年前の、あの「始まりの日」の私を目の前にして、クルリと回したなわとびを、ピョンと跳んでみたい。そうしたら、私も「なわとび名人」になれるかもしれない。