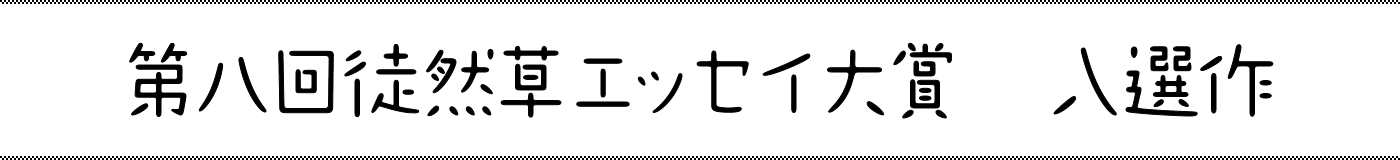
「こっちに帰って来て、先生にでもならへんか」
一九七二年、卒業間近だというのに就職活動を何もしていなかった私に、父が言った。
その頃の私は、何になりたいのか、何をしたいのかさえ分かっていなかった。
だから、仕方なく故郷に帰ることにしたのだ。
実家に帰ってからしばらくして、母校である小学校に産休を取る先生があり、その先生が職場復帰されるまでの四か月間、三年生の担任として勤めることになった。いわゆる、「産裏」と呼ばれる臨時教員である。
当初、先生としての仕事の右も左も分からない私は、全校の先生方のお世話になりっぱなしであった。
最初の一か月は無我夢中だった。
ただ、臨時教員ということもあり重要な校務を任されることがなかったので、昼休みは子どもたちと運動場で遊びまわった。
休み時間に運動場で見せる子ども達の顔は、教室で見せる顔とはまた違ってとても興味深い。
乱暴な言動の多いように見えていた子がドッジボールの苦手な子をあてるときにさりげなくゆるく投げたり、授業中おとなしい子が思いっきり愉快なお喋りを聞かせてくれたりする。毎日、子どもっていろんな顔を持っているなあと、楽しい発見の連続であった。
この昼休みの遊びは、子ども達と一緒に大笑いすることがあると自然に授業まで活気が出てくることを教えてくれた。
そんな昼休みの遊びのときに、気になる子がいた。
隣のクラスのF君だ。
その彼が、なぜか、自分のクラスではなく私たちのクラスの遊びを遠巻きに見ているのだった。
F君のことをよく知らなかった私は、
「F君、一緒に遊べへんか」
と気楽に声をかけていた。
F君の表情がサッと硬くなりその場を離れると、子ども達が口々に言った。
「先生、F君は学校では喋らへんねん」
「そっとしといたげたらええねん」
それで、他の先生方にもF君の話を聞いたところ、彼は場面緘黙で家では話すらしいのだが、学校では無表情で誰も一度も声を聞いたことが無いということだった。
ところが、元来お喋りな私はそっとしておこうにも姿を見たら声をかけたくなる。別に返事が無くても良かった。
廊下ですれ違うときに、
「次は、音楽か。楽しんできて」
トイレで出会うと、
「スリッパを並べてくれたんや。ありがとう」
給食室で出会うと、
「今日のカレー、美味しかったなあ」
と、話しかけていた。
他の子ども達や先生方から見たら、無駄なことをしているともF君の負担になるとも思えたことだろう。
でも、声をかける度、彼の表情が和らぎ、時にはうっすら笑顔さえ見せてくれるようになっていったのだ。そうなると、私は話しかけることが益々楽しくなっていた。
そして、四か月の臨採期間が終わろうとするある日、月一回の集団下校の時のことだった。
町ごとに並んで次々に下校していく子ども達は、各々、先生方に「さようなら」と挨拶したり手を振ったりしながら帰って行く。
私も子ども達に負けじと手を振り「さようなら」と大きな声をかけていたところ、F君の町が目の前を通り過ぎようとしていた。
その時、F君が満面の笑顔で私に手を振り返してくれたのである。
嬉しくて嬉しくて、私もちぎれそうなほど手を振った。
その後の職員室では、あのF君が笑顔で手を振っていたことに驚いた先生方が、大騒ぎだった。
「あんたは、ええ先生になる素質がある」
「子どもの心を引きつける何かがある」
と、しきりに持ち上げられた。
そして、単純な私は、その気になった。
その気のまま、その後三十八年間、小学校の先生として勤めたのだ。
始まりは、当時、「先生にでもなるか」「先生にしかなれない」とやる気と能力のない先生を揶揄して言った「でも・しか先生」だったけれど、この臨採期間の四か月で「先生こそ、私の天職や」と思い込むまでになっていた。
結局、私もF君の声を聞くことは無かったのだが、彼と笑顔を交わせたことが三十八年間の第一歩目だったことは間違いない