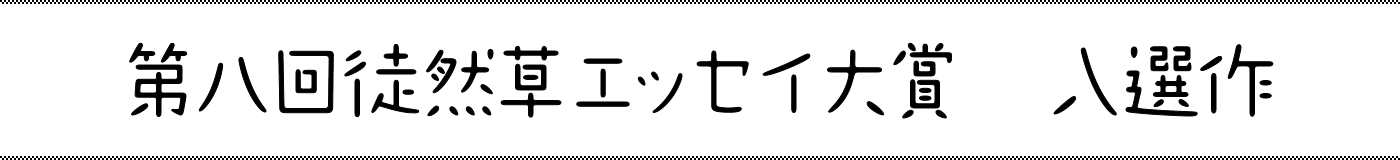
今日も行けなかった。目の前にかかっている制服を見て俯き、クローゼットをそっと閉めた。
高校入学初日の帰り道、数時間前の教室を思い出す。人付き合いが苦手な私は、進学する高校を小学校や中学校の知り合いが一人も来ないところに選んだ。周りではすでにグループができていた。輪に入ることもできず、ただ、淡い期待が沈んでいくのを感じた。
「友達、作りたかったなぁ」
友達が一日で作れるとは思っていない。しかし、一人くらい自分に話しかけてきてくれるのではないかと期待した。仕方ない、明日もある、と気を奮い立たせて、目頭が熱くなるのを必死で堪えて足早に帰った。期待とは裏腹に願いが叶う気配はなかった。数週間経つ頃には、温かく励ましてくれていた日差しも徐々に熱を帯びるようになり、焦りを表しているかのようだった。
もう、一ヶ月ほど学校には行っていない。二週間前から、いつもは朝ごはんの横に用意されていたお弁当も見なくなった。そのうち、学校には行けないまま夏休みに入った。学校から正式に休みであるとされているので、幾分か心が軽かった。
お盆になると母の実家に帰ることになった。母の実家は古い二階建ての一軒家で、主玄関から左の方に広い庭がある。今は祖母が一人暮らしだが、数年前まで母の妹である叔母が一緒に住んでいたと聞いた。
母の実家では、叔母の昔の部屋を使わせてもらった。叔母は本の虫らしく、部屋の本棚には大量の文庫本が並べられていた。やることがなかったため、その中から一冊拝借して読んでみようと思い、手を伸ばした。何を読もうかと迷っていると、背表紙にも表紙にも題名の書かれていない本を見つけた。不思議に思って中をみると、それは本ではなく文庫本サイズの日記帳だった。叔母の字だと思われる手書きの文字がなぜか冒険心をくすぐり、最初のページをめくった。綴ってあったのは高校の入学式の話だった。一瞬どきっとして手を止めたが、好奇心に負けて読み始めた。日記帳には校長の話が長かったことや、クラスメイトに対する不安、話しかけてくれる人がいなかったことなどが書かれていた。今の自分の気持ちをそのまま言語化されたような文章に不思議な高揚感と一抹の疑問を抱いた。なぜなら記憶の中の叔母ははつらつとしていて、自分と同じような考えはしない人だと思っていたからだ。それでも、言い表せない心の奥底の感情が自分だけではないと感じ、日記帳の叔母に親近感を持ちはじめた。日記帳には主に学校行事の出来事や感想、日常的な話が書かれていた。学校での話から推察すると、叔母と私がよく似た感性の持ち主だということを感じた。最後のページを捲って、私は動きを止めた。
「毎日がはじめましての私。記憶を輝かせる行動をする」
どういう意味かはわからなかったが、ひどく心が惹かれた。同じ人物からとは思えないような言葉がでてきていることが不思議だった。なぜ惹かれるのか考えようとして、夕食に呼ばれた。それから何日か、日記帳の最後の文章を反芻し、なぜ惹かれるのだろうかと思考を巡らせた。
結論、あの言葉の意味を説明できるのは叔母しかいないと思い、叔母に電話をかけた。叔母は昔の記憶よりも元気な声で、年齢の衰えなど感じさせないほど生き生きとしていた。叔母と話すのは数年ぶりなので、お互いにぎこちない挨拶を交わした。意を決して事の経緯を説明し、日記を勝手に読んでしまったことを詫びた。そして、最後の言葉がとても気になると伝えたところ、意外なほど簡単に返答が返ってきた。
「私は毎日が新しい始まりだと思ってる。そうすると、毎日私は新しくなった私と対面する。だから、毎日がはじめましての私。そして、今日も明日になったら昨日になる。でも今日のうちは明日の自分のために行動を選択することができる。自分を輝かせられる記憶を作る行動ができるの。高校生のうちに不安ばかりじゃいけないと思って楽に頑張れるをモットーに作った文章よ。つまりは、いつも新しい気持ちでいよう。少し勇気のいる行動を心がけてみようという意味なの。例えば今私に電話してくれたのも、小さいかもしれないけれど、勇気のいる行動だったはず。あなたからできる行動はいっぱいあると思うわ」
胸の鼓動が大きくなった。思い返してみればいつも受け身だった。自分から、なんて考えもしなかった。けれど、そんな私もできることがあるのだと叔母が言った。
お礼を言って、電話を切った。自分にもできることがある。少し考えてから、一階の台所に母を探しに行った。母に新学期からお弁当をまた作ってほしいとお願いすると、母は驚いた顔をした後、任せてと笑った。
九月に入った。新学期が始まる。今日の私へ、初めまして。お弁当を持ったかと聞く母に応答しながら、靴を履く。ドアノブを回して、母に挨拶をする。
「行ってきます」
今日もはじめてに踏み出す。