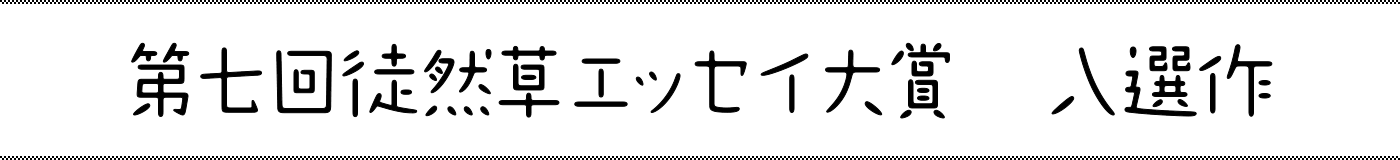
「七年間再発していないなら、安心してもいいんじゃないかな」
夏ももうすぐ終わる八月下旬、御茶ノ水駅の近くにある病院に併設された喫茶店で、診察に付き添ってくれた相方はテーブルの向かいで私に言った。診察では経過観察だった。朝食代わりに頼んだドーナツを食べながら、私はこの七年間を振り返った。思えば、最近は怯えることがなくなってきた。多発性硬化症の再発に。
最初の発症は七年前の九月、大学二年生の時だった。下宿していた横浜市のアパートはロフト付きの部屋だった。ある朝、強い頭痛を感じた私は、偏頭痛だと思い薬を飲み寝台に横になった。痛みが治まるのを待ち目を瞑る。ふと瞼をあけると、一階からロフトにまっすぐ伸びているはずの梯子がぐにゃりと曲がっている。寝ぼけているのだろうか。そう思ったが意識ははっきりしていた。周りを見渡すと空間自体が歪んでいる。詳しくは覚えていないが、そばにあるスマホに必死に手を伸ばし救急車を呼んだ。
運ばれた同じ横浜市内の脳外科病院でMRIを撮ると、脳に病変が見つかった。左眼の眼球の動きを司る部分に異常があるため、正常に動く右眼球と向いている方向がずれ空間が歪んで見えるらしかった。原因は脳梗塞かもしれない。医師は言った。命を奪うかもしれない病気の名前に私は怯えた。
急性期が落ち着くまで、そのまま入院することになった。
病院での朝は爽やかに迎えた。相部屋の中年の女性が毎朝六時前に窓を開けるからだ。少し肌寒い秋口の風で目が覚める。ぼんやりした意識に追い打ちをかけるように六時の院内放送が流れる。明るい演歌のメロディーが私を覚醒させた。昼になると、開いた窓から近隣の工事現場の音が入ってくる。男性の野太い声とドリルの荒々しい音。人々が生活を営む音は全く不快ではなく、むしろ安心感をもたらした。
二十一時になると、消灯の時間となり院内は真っ暗になった。しかし完全な静寂ではない。一つ下の階の重症患者のうめき声が途切れがちに聞こえる。
もう少し時間が経つと完全な静寂がやってくる。私は再び死に怯えた。瞼を閉じながら小学六年生の時に読んだ「ネシャン・サーガ」というドイツ人作家のファンタジー小説を思い出す。スコットランドの裕福な少年ジョナサンは足が使えず車いすの生活なのだが、夢の中ではヨナタンという足の自由な少年になった。ジョナサンは広い世界を冒険するヨナタンの人生を夢の中で謳歌する。次の朝、辛い寝台の上での一日が始まるとしても。ところがジョナサンは、ある日を境に完全に夢の中の世界に入り、ヨナタンになる。「ネシャン・サーガ」の扉には、古代中国の思想家荘子が詠んだ詩が書いてあった。
昨晩、わたしは蝶になる夢を見た。はたして今のわたしは、蝶になる夢を見た人間なのか、それとも人間になる夢を見た蝶なのか。
夢と現実の曖昧さを詠ったその詩の美しさに小学六年生の私はうっとりした。
しかし病院で寝ている今は、その詩を恐怖をもって思い出す。私は生きている夢を見ている死者ではないだろうか。荘子が人間であるか胡蝶であるかを確信を持てなかったように、私も確信が持てなかった。周りには静寂と濃い闇しかない。何が夢と現実の曖昧さを拭ってくれるのだろう。
ふと耳を澄ますと、新幹線の走る音が聞こえた。病院の南五〇mのところに、住宅街を見降ろすようにして北東から西南にかけて東海道新幹線が走っているのだった。幹線の上を人間を乗せた車輪が滑る音は、人々が生活を営む世界のものだ。私は確信を持った。これは夢ではない。私は今、現実を生きている。
その後もMRI検査や髄液検査、血液検査をした。脳梗塞は否定された。入院から三週間が経ち退院したが、原因はわからないままだった。横浜市の他の病院で、多発性硬化症の可能性があると診断された。今後も、脳の他の部位に病変が再発するかもしれない。次動かなくなるのは足かもしれないし、全身かもしれなかった。
あれから大学を卒業し、就職をした。もう七年も経ったが、目立った症状が出てこない。さすがに再発への恐怖は柔らんでくる。私はヨナタンではなくジョナサンだし、胡蝶ではなく荘子だし、死んだ人間ではなく生きている人間だ。その確信を脅かすものは何もない。
しかしなぜだろう。今でもあの音を聞くとはっとする。
御茶ノ水の病院に行って一週間後、九月初旬、駅を出て畑の中の道を歩いていた。木々に挟まれた細い道は途中からトンネルになっている。トンネルの上、歩く人の頭上わずか数メートル程のところに新幹線が走る幹線が敷かれている。トンネルに向かって歩いていると、ちょうど左側から新幹線が飛び出してきた。今は動く眼を使って、音を出す物体を見上げる。強い風が宙を切るような爽やかな音を聞いていると、心が浮き立つ。ときめく。私は確かに生きているよね、と。それは今、人生が未知なる領域へと進んでいることへの高揚感なのかもしれない。