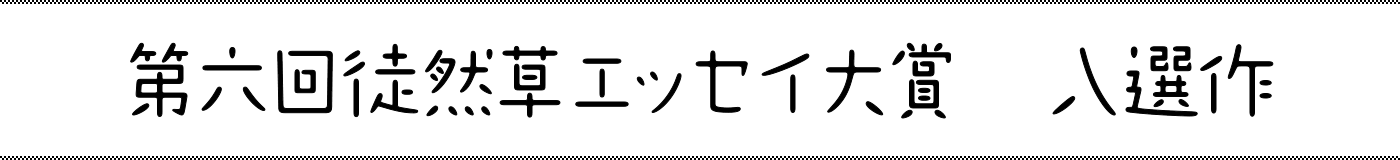
スマホが着信を知らせる。
「マーちゃんか? こんにちは。玲子です」
「あ、おばさん。こんにちは」
玲子おばさんは母の妹である。九十三歳の母は四人姉妹の二番目、玲子おばさんは末っ子で母の八つ下だ。長女と三女のおばさんはすでに他界されていて、二人は時々長電話でおしゃべりしたり、玲子おばさんが母を訪ねてくれたりしている。
母は半年前までアパートで一人暮らしをしていた。心配だから一緒に住むことを切り出しても、「まだまだ大丈夫。一人がええねん」となかなか首を縦に振らなかった。だから僕は経営する居酒屋の定休日である日曜日には、毎週母のアパートで親子二人の昼ごはんを食べていた。
父は三十七歳で突然この世から消えた。朝、元気に「行ってきます」と会社へ出かけ、夕方には心臓が止まった。まだ幼い僕と姉を残して。結婚生活十年目の、母が三十三歳の時だ。以来半世紀以上、彼女は再婚もせず一人で姉と僕を育て上げた。
そして姉の佳代子が五十八歳で亡くなった。癌だった。町田へ嫁いでからも姉はしょっちゅう母に電話をし、母が可愛がる孫を連れて家族でよく京都へ帰って来てくれていた。そんな最愛の娘に先立たれた母はさすがに憔悴した。生きる気力が萎え、睡眠薬なしでは夜も眠りにくくなり、パジャマ姿で過ごす日が増えていった。もう一人暮らしは限界が来ていた。
僕の家には僕と妻と次女、そして車椅子生活の義母が同居していたから、母まで家に呼ぶのは無理だ。そこで僕は、店の近くのマンションで僕が母と二人で暮らすというのはどうか、と妻に提案をしてみた。妻は、「今でも夜中に帰って来てランチの仕込みに朝から出かける毎日やから、遠い家に寝に帰ってるだけやもんな。店の近くの方が体もウンと楽やと思う。お義母さんもまだ元気やし介護ってほどでもないから、その方がいいかもな。こっちが女三人になるのがちょっと不安やけど、まあなんとかなるやろ」――。
母を説得し、二十年間一人で暮らしたアパートを引き払い、母との二人暮らしを始めて半年になろうとしている。朝、僕が出かけてから夜中に帰るまで母は一人で掃除をしたり洗濯をしたり、帰宅後に食べる僕の晩御飯を作ったりしている。帰ると、毎晩テーブルの上には母の手料理が並んでいる。そして必ずその横には広告の裏に書いたメッセージが。これとこれをチンしてとか、テレビの料理番組でやってたのを作ってみたとか、今日の鬼平犯科帳はすごく良かったとか、お漬け物に醤油をかけすぎないように、とかだ。
玲子おばさんが続ける。
「マーちゃん、今日の昼間お邪魔したえ。姉さん元気そうやったわ」。「ありがとうございます。よろこんでると思います」。「久しぶりに二人でゆっくりいろんな話をしてな、ほんで、これはマーちゃんに言うといてあげなあかんわ、って思て電話したんよ」。「はい? なんですか?」。「マーちゃん、あのな、姉さん、これまでの人生でいまがいちばん幸せなんやて」。「え……、そんなこと言うてたんですか?」。「うん。なんか私、うれしいてなあ。あの人ホンマに苦労ばっかりしてきたさかい」。「へえ、そうですか……、そんなこと言うてましたか……」。「九十三歳でいまがいちばん幸せって言えるなんてすごいことやなあって思って。それはやっぱりマーちゃんのおかげやなって思って。あんたがちゃんと姉さん寂しくないようにしてくれてるさかい」。「へえ……。でも、なんか僕は複雑やなあ。九十三でいまがいちばん幸せって、今日までいったいどんな人生送らせてきてしもたんやろって」。「マーちゃん、それはちがうよ。姉さんはもう昔すぎて忘れてるだけで、そら正雄さんとあんたと佳代ちゃんと四人で過ごしてた十年間があの人のいちばん幸せやった時やろと思う。けど、今また心底そう思えてることが大事なんや。ありがとうな。私うれしいてな、マーちゃんにお礼が言いたくなったんや」
電話口の僕は意外で、なんだか少し複雑な気分だった。けれど、余命宣告を受け、「マーちゃん、お母ちゃんのことごめんな。でもあんたによろしく頼むって言うしかない」と言ってた姉には少しだけ自慢したい気分だ。
九十三歳で「いまがいちばん幸せ」なんて、そんな哀しい人生であっていいはずがない。けれど、そんな言葉が口をついて出るのなら少なくとも母はいま、辛い毎日を送っているわけではないんだろう。そう思ったら、ほんの少しだけ僕の心は華やいだ。
そして僕は願う。心から願う。母が言った、いまがいちばん幸せの『いま』が、これから先もずっと『いま』でありますように、と。