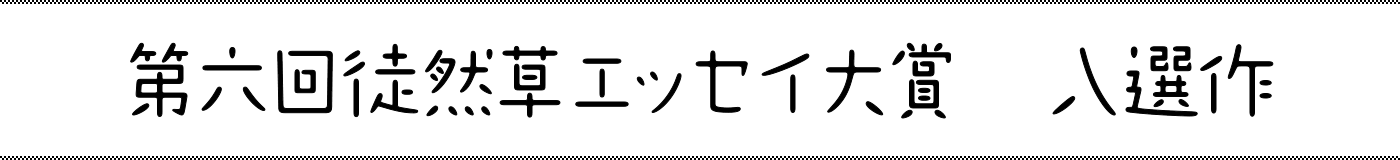
「忘れないでほしい」
これが一番の願いだと何度耳にしたことか。
沿岸部が波で表面を引き剥がされたようになってしまった地へ、私は災害発生の半年後から足を運ぶようになった。一年に二~三度、それぞれ二~三日の滞在で私のできることなど微々たるものだが、一つ言えることがある。
自分の足でその地に立ち、五感で直接触れることは、どんな膨大な量の映像をハイビジョンで見るより、はるかにわかるということだ。知るとわかるは大違いだ。
打ち上げられた泥だらけのアルバムを瓦礫とせずに、道の端に積む人が出てきた。そこから先、洗浄して持ち主に戻ることを願って活動する人たちに、私はボランティアとして混ぜてもらった。
現地のボランティアから、私のような他県からのボランティアに別れ際よく言われたのが、「忘れないでほしい」だった。
ある程度洗浄・乾燥できたものが溜まり、展示して、来場してくれた人と縁のあるものが見つかればお返しする段取りとなった。
展示返却会の趣旨に賛同してくださる方々から、たくさんの差し入れが届いていて恐縮した。その中に、花の種が入った紙の小袋がぎっしり詰まった箱があった。差し入れの意図が読めなかった。
「来場された方に自由に持って帰ってもらいましょう」
現地ボランティアの一声に私は己の発想力、想像力の乏しさを恥じた。
私は会場入り口での案内役として立った。瓦礫扱いを免れたのは写真だけでなく、身の回りのもの全般に及んでいた。合格証書など厚紙の筒はくたくたでも、中身はきれいに取り出せる状態のものもあった。名前が書いてあるので、そういったものはパソコンで名前と物品を管理していた。
二十代とみえるカップルが手を繋いでやってきた。 彼氏がパソコンコーナーへ来て、名前で検索を希望された。
「いろんな資格を取ったのを一冊のファイルにまとめてて…… 免許類は再発行できるけど、そういうのって記念品みたいな扱いで二度と手に入らないから、ないかなと思って」
検索すると見事ヒットした。早速本人に現物を見てもらうことになった。
出てきたのは一本のプラスチックの筒だった。首を傾げる彼氏。中から賞状が出てきた。
「夏休み日焼け大会 二位」
二人は顔を見合わせた。そしてみるみる頬が緩んだ。
「なんでこんなもんだけ出てくるかな……」
穏やかにがっかりする彼氏に、彼女は体を寄せた。
「いいじゃない。もらって帰ろ」
再び手を繋いで歩き出した二人に、幸あれと願わずにはいられなかった。
帰りがけの女性が、出入り口に箱ごと置いてあった花の種にじっと目を留めていた。
「ご寄付いただいたものです。よかったらどうぞ」
私より年上のその女性は、私の首からぶら下がる名札の都道府県名を見て「遠くから来てくれてるのね」とだけ言い、花の種に視線を落としたまま手に取ろうとはしなかった。
私がそっと離れようかとした時、「あのね……」と顔をあげた。
「私の主人、お花作りがとっても上手だったの。海のそばの広い土地にいっぱいお花を作って、いい暮らしをさせてくれたの。でも今は仮設住宅でプランター一つさえ置けない。こんな種もらっても仕方ないの」
私はうなずかず、返事もせず、傾聴した。
「でも……。プランターくらいならなんとか置けるかしら。蒔いてみようか、私も……」
袋をおそるおそる手にとり選び始めた。
「これとこれ二つもらっていい?」
「もちろんです」
「ありがとうね、聞いてくれて」
女性の背中に向かって、お花を目にするのが辛くない日が訪れることを願った。
私と同年代と思しきご夫妻が来られていた。夫は一刻も早くこの場から去りたそうに落ち着きがなかった。妻はゆっくりと踏みしめるようにしか先へ進まない。
「もうこんなの誰のか分からないって。行こう」
夫は先を急かした。
すると、ノート類が並べてあるコーナーで妻が歩を止めた。一般に広く市販されている作文帳の、ある一冊の表紙を凝視したまま動かない。表紙の名前は水性ペンだったのか、消えていた。一度濡れているので、ほとんどめくることができなくなっているページを、妻はめくろうとした。真ん中あたりでなんとか見開けるところにあたった。中は鉛筆書きで文字が読めた。妻ははらはらと涙をこぼした。
「大工になりたいって書いてある。これうちの息子のです」
ノートを胸に抱きしめ「お父さん、私、呼ばれた気がしたの」。
子供をあやすようにノートを優しくさする妻の肩を、同じようにさする夫。このご夫妻がいたわりあって、今後を過ごしていかれることを切に願った。
絶対に忘れない。未曽有の災害があったことも、それでも生きていく人がいることを。