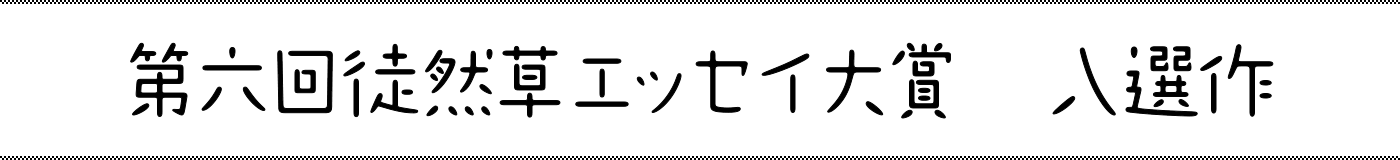
「今ならばまつすぐに言ふ
夫ならば庇つて欲しかつた医学書閉ぢて」
これは現代歌壇を代表する歌人河野裕子さんの歌だ。乳がんを患った河野さんに対し、細胞生物学者である夫の永田和宏さんは、医学書と首っ引きで医学的な話ばかりしていたのであろうか。あるいは妻を安心させるため、あえて平静を装っていたのであろうか。しかし、妻としては、闘病の辛さを受け止めてもらいたい、今後どれくらい一緒に暮らせるかわからない夫婦の時間を大切にしたいという願いが強かった。私はこの歌を読んだとき、自分が犯した過ちを思い出した。
二〇一二年の冬は例年以上に寒さが厳しく、強風が吹き荒れていた。当時私の妻は、生まれて初めての抗がん剤治療を受けていたが、家に引き籠っていたら体力が落ちるからと、毎日散歩に出かけた。しかし、抗がん剤の副作用と折からの強風のために、いつも途中で歩けなくなり、何度も道端に座り込んで休まなければならなかった。そして、疲れ果てて家に帰ると、
「情けない……。本当に情けない。散歩もできない体になってしまった……」
と涙を流すのであった。そんな妻に私は、妻の病気に関する耳障りのいい医学情報を調べてはまくし立てた。それが妻を励ますことになると思っていたのだ。
その後、妻の病状は一進一退を繰り返しながらも徐々に悪化し、四年前の夏、ついに余命二か月の宣告を受けた。このとき私は、主治医の話を頑なに否定した。もう妻の命を救う方法がないことは頭では理解していたが、感情が受け入れなかったのだ。
治験情報や学術論文を調べ、医療機関に問い合わせた。大学の研究機関で先進医療の研究開発に関わっていた息子に頼んで、いくつかの研究機関や大学病院にも照会してもらった。その合間に入院中の妻に会いに行ったが、あまり長居もせず、耳障りのいい情報を一方的に話すばかりであった。後になって思い返すと、私の話を聞いているときの妻の表情は寂しげで、返事も少なかったように思う。妻のためと言いながらも、私は自分自身が希望を持ちたかっただけではないだろうか。そんな情報など妻は望んでいなかったのではないだろうか。
余命の二か月が過ぎようとしていた十月三十日。妻は二か月前から絶食中だったが、数日前から病状が落ち着いていたので、その日のCT検査が終わった後、少しなら固形物を食べてもいいという主治医の許可が下りた。
「CTが終わったら少しなら好きな物食べてええよって先生が言うてくれたよ。私、あそこのコンビニの卵のサンドイッチとコールスローサラダとシュークリームが食べたいな」
と妻は窓から見えるコンビニを指さした。食べ物にはこだわりが強い妻が、あえてコンビニの軽食というのはどういうことなのだろうかと私は不思議に思った。
「コンビニでええの? デパ地下の名店街で何でも買うてくるよ」
しかし、妻は強くこだわった。
「あのコンビニのがええのよ」
妻がCT検査を受けている間に、私は妻に言われたとおり、病院のすぐ向かいにあるコンビニに行き、妻の分と私の分の食べ物を買った。CT室から戻った妻は、私が買ってきた食べ物を少しずつ口に運びながら、とりとめのない世間話をした。しかし私は、「ちょっとずつ、ゆっくり食べんと体に悪いよ」、「体調はどう?」などと体調ばかり気にして、あまり妻の話に受け答えをしなかった。
妻は少し食べると、「心配かけてごめんなさい。もう十分。あとは徹さんが食べて」と残りを私に手渡した。
その夜遅く私が家に帰ると、病院から電話がかかってきた。妻の病状が急変したという知らせであった。それ以来、妻は意識が混濁した状態が続き、ほとんど会話らしい会話もできないまま、数日後に息を引き取った。
病室で妻の亡骸を自宅に連れて帰る準備をしていると、引き出しからメモ帳が出てきた。主治医や看護師の話などの備忘録として使っていた妻のメモ帳であった。
その最後のページを開くと、妻の最後の文章が残っていた。
「CTから帰ってから、徹さんとコンビニの卵サンド、コールスローサラダ、シュークリームを食べた。とっても美味しかった。最後に食べられたのが徹さんと一緒で良かった。本当に良かった。何より二人で食べられたのが良かった。最高の幸せだと思う」
今となっては妻の本心を知ることはできないが、妻が最寄りのコンビニにこだわったのは、少しでも私と一緒にいる時間を増やしたかったのかもしれない。このメモ帳を読み終えたとき、私は何ひとつ妻の願いに正面から向き合わなかったことに気づかされた。