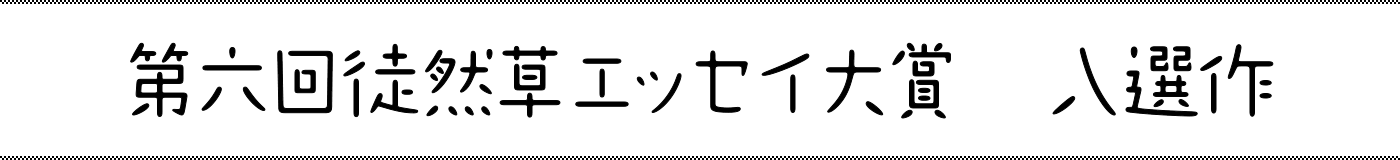
私には、十九の妹がいる。
溌溂とした、愛嬌のある、ほんとうに賢い子だ。笑ったときにできるえくぼが可愛らしくて、あどけない子だった。
去年の六月、家族全員で出かけた温泉旅行の帰り道で、私たちは交通事故に遭った。記憶はない。両親と私は重傷を負い、妹は脊髄損傷によって、四肢が麻痺状態になった。妹は寝たきりになった。意思疎通は、口を軽く動かして行うようになった。妹は、笑わなくなった。
妹は本が好きだった。私は週二度、妹のいる病院へ行って、彼女の好きな小説を読んで聞かせるようになった。はじめて物語を読み聞かせた夜、私は妹に、
「どの時間が一番楽」
と聞いた。時間潰しのつもりだった。妹は、
「よる」
と言った。続けて、ゆっくり、
「だって、かんがえなくて、いいもの」
と言った。私はその日、病室から家へ戻って、ひとしきり泣いた。妹がどんなことを、どんな瞬間のことを考えているのか、想像したくもなかった。私はまた、彼女が送るはずだった大学生活のことをふと考えてしまって、泣いた。俺が弱くてどうする、と思って、事故の日から習慣にしている日記を泣きながら書いて、寝た。
それから、三カ月ほど経った。その頃、私は妹に、『斜陽』という、長い小説を読み聞かせていた。それは、没落してゆく旧家の人間たちを描く、太宰治の小説だった。話の途中で彼女を放っておくわけにもいかず、私は毎日病院に通って、『斜陽』を読み聞かせた。一文ごとに彼女の顔を覗きながら、間延びするほどゆっくり、読んで聞かせた。
その日の夕方、物語は佳境に入って、病室には私の声だけが響いた。
けれども、私は、幸福なんですの。私の望みどおりに、赤ちゃんが出来たようでございますの。私は、いま、いっさいを失ったような気がしていますけど、でも、おなかの小さい生命が、私の孤独の微笑のたねになっています――
そこまで読んで、私は耐え切れなくなって、とうとう黙り込んでしまった。視界が歪んだ。妹を見ると、なぜか笑っていた。そして妹は、あ、い、あ、お、う、と口を動かした。私は、いつも私がそうしているように、あ、り、が、と、う、かな、と聞き返す。
うん、ありがとう。
妹の肉声が、確かに聞こえたような気がした。妹の笑顔を見たのは久しぶりだった。笑ったときに浮き出る彼女のえくぼが、私のことも自然と笑顔にさせた。
私はこれまで、これは本当に傲慢かもしれないが、私の存在が、多少なりとも妹を生かしていたような気がしていた。本を読み聞かせる時間が、彼女にとって一瞬でも、癒しになっていれば良いと思っていた。生きる理由になれば良いと思っていた。けれど、そうではなかった。生かされていたのは私の方だったのだと、ようやく気づいた。
彼女と向き合い、ひとつの物語に入り込む時間のすべてが、妹に対する愛情と、あの日妹を襲った悲劇を、鮮烈な記憶を、私の中でやわらかく消化していた。
「俺も、ありがとう」
そう言うと、妹は照れくさそうに、また笑った。落ちてゆく日が、無機質な病室を真っ赤に染めていたのを、今でも覚えている。
あれから妹は、すこしだけ指を動かせるようになった。私は、彼女がすっかり健常者に戻ってしまうというような、果てしない希望は決して持たない。ただ私は、病室で妹と共に巡った素晴らしい世界のことを、二人で夜通し語りあえる日を、今も待っているだけである。