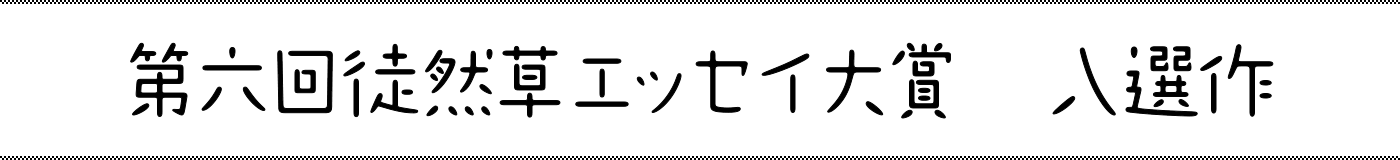
十六年前の六月。梅雨入りのニュースが流れる中、私は無菌室のベッドに横たわっていた。これから見知らぬ誰かが提供してくれた骨髄液による「骨髄移植(造血幹細胞移植)」を受けるために。
突然、急性骨髄性白血病との診断を受けたのは三十四歳の冬。当時、働き盛りの夫と五歳と六歳の娘がいた。今死ぬわけにはいかない、と必死に治療に耐えた。その甲斐あって一時は「寛解」となったが、残念ながら二年後に再発。次の治療は骨髄移植しかない、と言われていたが、骨髄液の適合する家族がいない。そこで骨髄バンクに登録し、骨髄ドナーを探すことになった。一年半待って、ようやく私は一人のドナーさんに出会うことができた。出会うと言っても守秘義務のためお互いの素性は判らない。「九州在住の三十代の男性」。相手の情報はただそれだけ。赤の他人であるこのドナーさんとの不思議なご縁は、この後私を四度、救うことになる。
骨髄移植は無事に終了。二週間程でドナーさんの細胞が新しく血液を作り始めた。もうこれで安心……と思いきや、そこからが一番
辛い闘病生活の始まりだった。ともかく辛い。眠れない、食べられない、話せない、動けない。熱は下がらず、口や内臓の粘膜はダメージを受ける……ともかく今までの治療とは比較にならないほど一分一秒が辛かった。追い詰められた私は、ふと「ここまで頑張ったんだから、もう楽になりたい」と考えるようになっていた。この時が一番、肉体的にも精神的にもギリギリの状態だったのだろう。
そんな時、ドナーさんから一通の手紙が届いた。骨髄バンクではお互いに限られた内容ではあるが、手紙のやりとりができる。実はその手紙は、移植を受けた日の夜、私に代わって夫が感謝の思いを綴って出した手紙の返事だったと後で知った。受け取った手紙には「私こそ良い経験ができました。機会があればまた提供します」とあり、続けて「私が患者さんにできることはもうありません。今はただ願い祈るだけです。もうすぐ七夕です。祈り願うにはぴったりの季節です。これから私にできることはただ患者さんが回復しますようにと願い祈るだけです」と書かれていた。
その手紙を読んで私は一瞬でも「楽になりたい」と思ったことを激しく後悔した。見ず知らずのドナーさんが自分一人の命のために力を尽くしてくださったこと、今もこうして願い祈ってくれる人がこの空の下にいること、それに気がついた時、辛い治療に立ち向かう力が湧いてきた。そのおかげか秋には無事退院し、翌年には社会復帰を果たすことができた。
しかし試練は再びやってきた。四十六歳の時、今度は両胸に乳がんが見つかったのだ。またか……という絶望と、もう辛い治療はしたくない、という気持ち。十年前諦めていた娘達の成長もある程度見ることができた、後は静かに自宅で逝きたい、という思いが次第に強くなっていった。実際、大きな既往を抱えた私の治療は考慮する点も多く、半ば諦めにも似た気持ちで勝手に覚悟を決めた。そんな時、娘が一言こう言った。
「お母さんの命はドナーさんから頂いた大事な命なんだよね」。この言葉で私は我に返った。「そうだ、この命は頂いた命なのだ、乳がんなんかに取られてたまるか」と。気を取り直し、両乳房を切除する手術と抗がん剤、放射線治療を受けることを決め、生きる方を向くようになった。これがドナーさんに救われた三回目の出来事となったのだ。
そして昨年、最愛の夫が六十一歳で急逝した。闘病を繰り返す妻を全力で支え、娘達をこよなく愛し、家族のために生きてくれた突然の夫の死は、自分の病気以上にショックだった。夫の通夜の前日、いっそ後を追ってしまいたい、今なら同じ棺に入れてもらえる、と慟哭の果てに考えていた。
そんな時、同病の友人からメールが届いた。それは「悲しみや苦しみは想像を絶するけれど、私達はドナーさんから頂いた命を生きている。その命を最後まで使い切ろうね」という内容だった。瞬間、私は再び思い直した。「この命は夫が生きて欲しいと願った、あの夜暗い病院の待合室で、ドナーさんに御礼の手紙を書いてくれた、大切な命なのだ。生きていかなきゃダメだ」と。そして悲しみを抱えてでも生きていこう、と決心した。
あの時、願い祈ってくれた「もう一人の自分」でもあるドナーさん。できるならお会いして直接御礼を言いたいが、相手を知ってがっくりされるのも申し訳ないので、会わないままの方がいい。主人は手紙に「あなたは骨髄液だけでなく、私達家族に勇気と希望もくださいました」と書いていた。今、私はドナーさんとそのご家族が健康で幸せに暮らしていることを心から願う。そして全ての患者さんに生きる希望と勇気、骨髄移植を受けるための善意の骨髄液が届くこと、もっと言えば過酷な治療を受けなくても、白血病が治る日が来ることを心から願っている。