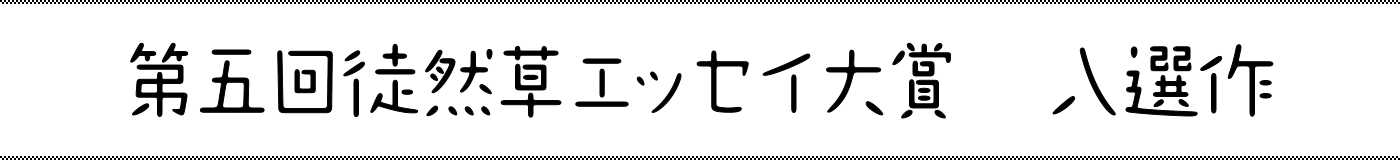
八月五日に祖父が老衰で亡くなった。九十九歳の大往生だった。家族はみんな祖父の事を「じいじ」と呼んでいたが、この祖父、とにかく「スーパーじいじ」だった。三年前、一緒に住み始めて最初に驚いたのは、僕の塾の難しい数学プリントをスラスラ解いたことだった。トンカツが大好物で毎日晩酌までしていた。通っていたデイサービスでは、最高齢だったのでよく代表でスピーチを頼まれていた。決まり文句は、「百二十歳まで頑張ります。皆さんも一緒に頑張りましょう」。帰宅すると「拍手喝采だった」とよく自慢していた。
そんな祖父が今年に入ってから少しずつ食べる量が減ってきた。病院で調べてもらっても悪い所はなく、年齢によるものだろうと言われていた。その後も食事の量は減っていき、七月になると口にするのは飲み物とアイスクリームやゼリーだけになった。僕が「もっと食べさせたら、また元気になるんじゃないか」と言うと母はこんな話をした。
母は少し前から祖父を病院ではなく自宅で看取ることを考えていたらしい。コロナ禍では入院するとその後なかなか面会できなくなってしまうからだ。だから家族に見守られながら出来るだけ幸せな最期を迎えられる様に、かかりつけの先生に話を聞いたりネットで調べたりしていた。人は最後の時が近づくと誰でも食べられなくなってくる。それは自然な形でその時に無理に食べさせたり飲ませたりすると消化しきれず、体がむくんだりひどい時には体から水分がにじみでてきたりして本人にとってはつらいらしい。たしかにその頃祖父は自分から欲しがった冷たい飲み物を、見ている方がうれしくなるくらい本当においしそうに飲んでいた。
夏休みに入ると、祖父はトイレに行くにも車イスと誰かの支えが必要になって、僕も手伝うようになった。やせて軽そうに見えた祖父も、自分ではもう力が入らなくなってきていたので意外なほど重かった。それでもまだ会話はしっかりしていて「天国から迎えに来るんやけど追い返してるんや。でもあと十日かなあ」と予言めいた事を言っていた。
亡くなる前日は、虫の知らせだったのか僕たちは何度も祖父の部屋に行って、体をさすったり顔をなでたりした。会話はもうできなくなっていたけど、「また来るね」と部屋を出ようとすると、「あぁ」と声をあげて引き止めているみたいだった。だから何度も行ってたくさん時間を過ごした。
次の日の朝、祖父は息を引き取った。まるで眠っているようなおだやかなきれいな顔だった。あの予言からちょうど十日目だった。やっぱり「スーパーじいじ」だと思った。
僕は今、受験勉強の休憩によく祖父の部屋に行って過ごす。なぜか落ち着くからだ。きっと見守ってくれているからだと僕は信じている。