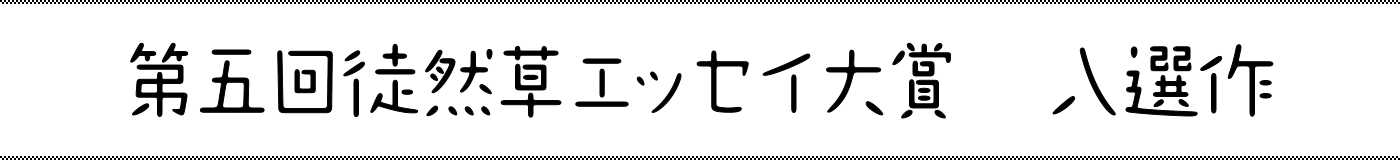
大学一年生の夏、私が所属するバスケットボール部の合宿先は長野県の諏訪だった。大会前の大事な強化合宿にもかかわらず、私は扁桃腺を腫らし高熱を出して宿舎で寝込んでしまった。そんな時、幼少時代に父から聞いた話を思い出した。
「うちの先祖で、富山から身延の寺に参拝する旅の途中、諏訪で病に倒れ、そのまま亡くなった人がいる」
父方の先祖の中でも、元祖といわれる小澤利藤は、戦国時代に尾張から北陸に移り、越中新川郡の代官を務め、この地に根をおろした。利藤の長男の家系は加賀藩士として幕末まで続いた。いっぽう利藤の次男の家系は、前田家の本陣として豪商「小澤屋」として栄えたが、祖父の代からは父も含めて医者家系になった。そんな中、諏訪で急死した先祖は誰か、どこの寺に埋葬されたのか全く不明だった。私は合宿所で熱に浮かされながら「諏訪で斃れた先祖の墓をいつか突きとめたい」という思いが芽生えた。
それから三十五年、私は東京の大学病院で小児心臓外科の執刀責任者になっていた。しかし五十歳の時に「虫垂癌」という予後不良の稀な癌にかかって緊急開腹手術に及び、七〇センチ以上の消化管を失ったうえに抗がん剤治療も受けた。まさに「外科医として人を切る立場」から「癌患者として人に切られる立場」になった。おかげで「患者とその家族が抱える痛み、苦しみ」を心から共感できる医師に進化した。
そんなある日、実家から思わぬ連絡が入った。祖父母の遺品から古文書が発見されたという。「小澤与三、明治十四年五月死去、上諏訪 髙国寺」と書かれていた。これはまさに諏訪で斃れた先祖のことだった。小澤与三は私の祖父の祖父、すなわち高祖父にあたる人物で、幕末の一八四五年に生まれ、十七歳で小澤屋当主となり県会議員も務めたが、一八八一年三十五歳の若さで身延山参拝の旅路で斃れた。高祖父の墓が果たして今も存在するのか、私は、いてもたってもいられず、諏訪の髙国寺を検索して電話をかけた。
「そちら様に、明治十四年頃、旅の途中で病に斃れて埋葬された小澤与三という者の墓はありませんか? 私は故人の孫の孫です。長く無縁仏にしてしまったようで……」
すると住職と思われる方が穏やかに答えた。
「しばらくお時間をください。これから調べてみます」
それから数時間が経ち、髙国寺から電話があった。
「お墓は、山門の裏にございました。ただ苔むしてしまい墓石の文字が読みづらくなっています」
このうえない朗報であった。私はあまりにうれしくて御礼の言葉を何度も重ねた後、墓参の日程を交渉した。
九月の晴れた日に髙国寺に到着した。紺碧の空を背に、山門に咲きほこるサルスベリの花の桃色がまぶしかった。ご住職に温かく迎えられ、さっそく高祖父の墓に向かった。 墓石は帯状の苔と共生していたが、「越中 小澤与三」の文字が確かに刻まれていた。
追善供養はしめやかに営まれた。おそらく高祖父は一四〇年間、自身のためだけに贈られる供養を知らない。お経の音色は澄んだ秋風に乗って心地よく響き、墓石の苔についた露は陽光を受けてきらめいていた。
読経の後、私はご住職に尋ねた。
「高祖父は、身延の寺に向かう途中で斃れたのでしょうか? それとも参拝の後で斃れたのでしょうか?」
するとご住職は、「それはわかりません。しかし一〇一歳になる祖母が健在ですので、連れて参ります」
ほどなく御祖母様が現れた。凛とした優美な気品にあふれていた。
「あなた様のご先祖ですが、身延山にお参りされた後、諏訪の宿に立ち寄られてチフスで亡くなったと伺っております」
それを聞いて私は救われた気がした。高祖父が参拝の目的だけでも果たせていたのなら幸いである。
さらに私は切り出した。
「高祖父の骨を富山の菩提寺に分けて頂けないでしょうか?」
御祖母様は間髪を入れず、「残念ながら、その時代は火葬ではなく土葬でしょう。もう骨は土に還っています」と答えた。私の要望は潰えたが、それでもひるまずに言った。
「では、墓土だけでも戴けないでしょうか?」
それには御祖母様もにっこりと首を縦に振って下さった。私はさっそくシャベルを借りて、高祖父のDNAが微量でも混じるように必死に墓土をかき集め、小さな骨壺におさめた。何度も頭を下げてお礼を述べたのち、諏訪を後にした。
私は意気揚々と、高祖父の墓土が入った骨壺を抱えつつ、富山の菩提寺の墓下におさめた。高祖父の長旅はここに完結した。
私が行動を起こして髙国寺を探さなければ、高祖父の旅は再開されず帰還も叶わなかった。しかし実は、高祖父自身が一四〇年間に及ぶ旅の最後に、癌で死にかけた子孫の私を敢えて選び、いざなってくれたのかもしれない。広大な緑の田園地帯を走り抜ける列車の座席で、私はそんなことを考えていた。同時に、高祖父の魂に包み込まれているような、温かい気分にひたっていた。