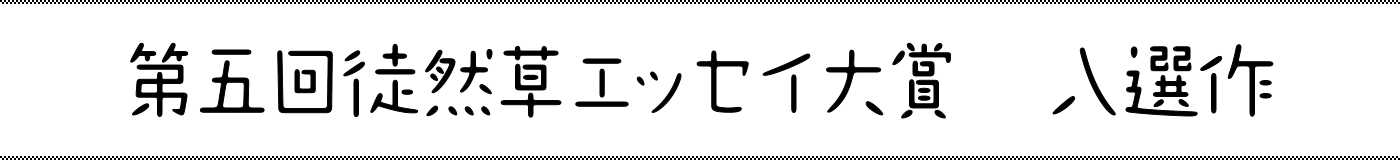
結婚披露宴会場では、新郎新婦がお色直しを終えた。そして入場のために扉が開かれた。スモークの中からライトに照らされた新郎新婦が浮かび上がってくると、会場から驚きの声があがった。
二十年以上前、私は車の修理工場でアルバイトをしていた。そこは社長と奥さんと娘さん、そして私が「先輩」と呼んでいた整備士の青年だけで営んでいる小さな工場だった。しかし、社長が長い間をかけて築いた信用のおかげで、工場はいつも大忙しだった。私の仕事は、洗車や雑用など社長や先輩の手伝いをすることだった。奥さんと娘さんは事務作業を担当していた。
初出勤の日、私は社長から作業着を受け取った。
「つなぎ服だ。アルバイトと言ってもこの工場の従業員として、丁寧に車と向き合って欲しい。今日からよろしく頼むよ」
年季の入ったつなぎ服を着ている社長は、私の肩を優しくたたいた。
社長は私のことをいつも気にかけてくれた。仕事に対しては厳しかったが、仕事が終わると先輩と三人でお酒を飲んだりもした。奥さんと娘さんも、田舎から出てきて一人暮らしをしている私に、何かと世話を焼いてくれた。同じく一人暮らしの先輩と一緒に夕食を食べさせてくれたり、つなぎ服の洗濯もしてくれた。ベランダに揺れるつなぎ服は、まるで会社の看板のようだった。
仕事にも慣れてきた頃、私はあることが気になっていた。それは社長の服装だった。社長は仕事の時以外でもつなぎ服を着ているのだ。仕事を終えると、社長は新しいつなぎ服に着替えていた。夕食を食べる時、友人に会いに行く時、町内会の盆踊りにさえ、つなぎ服を着て参加するのだった。休日にみんなで旅行に出かけた時も、社長はつなぎ服を着ていた。私は先輩に聞いた。
「俺も社長の私服を見たことがないな。もしかして、つなぎ服が体にひっついているんじゃないのかな?」
先輩は笑っていたが、社長のもとで十年以上働いている先輩でさえ、社長の私服を見たことがないということは驚きだった。後日、私は奥さんに聞いてみた。
「そうよ、あの人は一日のほとんどをつなぎ服を着て生活しているわ。この前なんか、ゴルフもつなぎ服でやったらしいわ。よくゴルフ場が許してくれたものよ」
奥さんは呆れたように話していたが、どこか楽しそうだった。
「あの人にとって、つなぎ服は特別な服なの」
社長は中学を卒業すると車の製造工場に就職した。そこでは、“新品”のつなぎ服が支給された。実家は裕福ではなく、兄弟もたくさんいたため、社長は今までボロボロのお下がりしか着たことがなかった。そんな社長にとってこのつなぎ服は、初めて着る新品の服だった。そして、社会と繋がった証だったのだ。社長は嬉しくて堪らなかった。
「それからずっとつなぎ服を着たまま。あの人とつなぎ服は人生の相棒よ。いつでも二人で力を合わせて、みんなに幸せを繋いでいるのよ」
それからしばらくして、娘さんが結婚することになった。相手は先輩だった。先輩は婿養子として、将来社長の後も継ぐとのことだった。私は驚いたが、社長と奥さんは嬉しそうだった。二人にとって先輩は、誰よりも信頼のおける存在だったのだ。
お色直しを終えた二人は、何とつなぎ服姿だった。それは、普段社長が着ているものだった。会場がざわめく中、娘さんのスピーチが始まった。
「先日、父が言っていました。結婚式にはつなぎ服を着て出ると。私達は冗談はやめてと笑っていましたが、実は、父には内緒で私達が着る計画を立てていたのです」
紋付袴に“着られている”社長は、ボカンと口を開けていた。その隣では、こちらもこっそりとつなぎ服に着替えていた奥さんが大笑いしていた。
「このつなぎ服に染み込んだ汗と油は、父の家族への愛の証です。これからは、私達がこのつなぎ服の後を継いでいきます。そして父の想いを繋いで行きます」
今でも、つなぎ服を着て過ごしたあの日々は、心の制服として私の大切な一着となっている。そして、社長がみんなに繋いだ優しさや真心を、私も誰かに繋いでいきたいと思う。