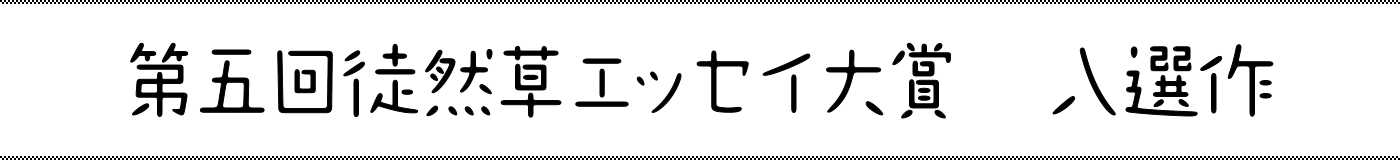
妻の月命日、朝七時に携帯が鳴った。
発信者に驚いた。数年ぶりだ。
「オババか」と言うと、少し間をおいて「あ、」と小さく驚いたような女性の声。
東京本社勤務のころ、お世話になったパートの掃除のおばさんだ。私とは同期だった。
私が東京へ単身赴任になると、おばさんが同期会を作ってくれた。私より一回りほど年上なだけのシングルのおばさん。いつしか皆が親しみを込めて「オババ」と呼んでいた。
夫婦喧嘩でウジウジする同期に「何やってんだよ!おたんこなす」と、愛情をこめてしかり飛ばす母親のような存在だった。
やがて会社の業績が下がり始めるとその会も数人に減った。退職者も出始めたのだ。会社は非正規を先に解雇し始めた。やがてオババにもその波が来るに違いなかった。オババにはまだ学生の娘さんがいた。
そこで相談して、オババを会社にとってオンリーワンの存在にしようと画策した。会は「オババを守る会」という名前に変えた。
得意なヤツがオババにエクセルを教え、掃除用具などの消耗品の在庫と経費管理をするプランをオババに提案し、目標数値も設定した。仕事の合間や休憩時間を利用してオババは必死で覚え、一ケ月でマスターした。私が、彼女はこんなことを自主的にやっているらしいと、噂話のように上席に言った。
嵐はオババを通り過ぎ、オババはみんなの前で「ありがとう」と涙ぐんだ。「泣くな」とみんなでオババのために乾杯して飲んだ。
そんなことがフラッシュバックした。
結局、私は二十六年間勤めた会社をいろいろあって退職した。やがてその会社は買収され、オババも辞めた。オババたち仲間にはときおり電話はしていたが、ガンで闘病する妻の看病でここ数年は連絡をしていなかった。
そんなときの嬉しい電話だった。
「ごめんな~。指があんまり動かんし、スマホに慣れてないから、電話帳の最初のあんたの名前を押してしまったんや」
それだけ言うのにオババは数分かかった。
「間違いでも嬉しいで、オババ」
オババは小さく笑った。エクセルと必死に格闘しているときの顔が浮かんだ。でも久しぶりに聞く声は江戸っ子の歯切れの良さはなく強張り、くぐもっていた。八十歳近いオババの体調がよくないことはわかった。
「体調はどうや」と気づかぬふりで聞く。
「ガンや。もうダメ。全身転移してるんよ。いまカンワの病室や」
驚く私にオババはしゃあないわと笑う。それより仲間の一人は同じガンで苦しみ、よく夫婦喧嘩していたヤツは熟年離婚したという。
「あんたは変わらんの? 奥さんや子供たちも元気?」とオババ。
「元気やで」妻はオババと同じガンでもう亡くなったとは言えなかった。
「それよりオババのお握り、懐かしいな」
「うん、あんたよく食べてくれたなあ」
娘の弁当のついでやからと、単身赴任の私に時折、お握りを持ってきてくれた。鮭や梅干しと一緒にオババの手の温もりも残っていた。掃除で荒れた小さな手が握るお握りを、母を知らない私は好きだった。
いやそれだけではない。オババの名前はアキコ。三歳にもならない私を置いて出ていった母と同じ名前だ。だから人より余計にオババに私は母を感じてしまうことがあった。
そのオババの命が消えかけていると知った私は疎遠にしていたことを恥じ、詫びた。
スマホの操作ミスではない。シャイなオババは私への電話を照れたのだろう。
「俺は小さい頃母親を亡くした。それでオババのお握りは母のお握りみたいだったんや。オババごめんな連絡せんといて。でも、もうダメなんていうな。いいか、絶対長生きするんやで。オババを守る会はまだ健在やで」
生死のわからない自分の母に言った言葉だったのかもしれない。オババはもつれた舌をほどくようにゆっくり話した。
「ありがと、嬉しいな。じゃ向こうでもお握り用意しとくわ。でもゆっくり来るんやで」
電話を切って私は、人生で利害関係の全くない友人は何人いるのだろうと考えた。何年も会わなくても、まるで昨日も会ったように話ができる友人は誰と誰だろう。数人しかいない。いや数人もいる。親もなく老いて妻も亡くし絶望していたが、その友人たちとなら、いつでも何でも話ができるじゃないか。その一人を失いそうになってはいるが、本当は、私は幸せ者じゃないかと思いなおした。
数日後、また電話が鳴ったが出る前に切れた。オババだったが電話しても出ない。
「オババ、逝くな!」とメールすると、「ごめん、めいわ」と寸足らずのメールが帰ってきた。ふと今回は「さよなら、向こうでまたね」の合図だったのではないかと思った。
「きっとまた会おうな、オババ」と涙の中で送信したが、もう返事は来なかった。