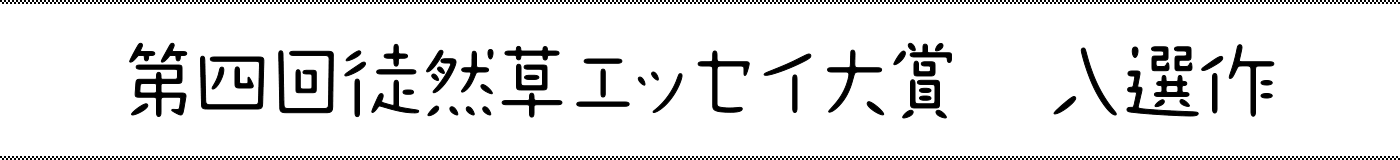
ガラガラガラー。病室のドアを開ける音がひびく。おばあちゃんは具合が悪いらしく、個室に移された。弟が生まれた年なのでまだ私は六才だ。おばあちゃんはがんや認知症などの病をかかえていた。
おばあちゃんのむすこ、私のお父さんのことはあまり覚えていないのに、私のことはよく覚えてくれた。そのことは本当にうれしく、私はおばあちゃんにとって大切な存在だったと気付く。そんなおばあちゃんが死んだのは弟が一才にもならない時だった。
おばあちゃんは大福が好きで私はきらいだった。しかし、おばあちゃんは私が大福をきらいだということを知らず、きっと喜ぶ! という目でくれた。うえっ!? はき出したかった。あんこの食感、思い出すと気持ち悪くなりそう。しかし私はのみこんだ。おばあちゃんは、にこっと笑った。私も、苦笑いした。
家に帰って数日がたったころ、おばあちゃんの病が急変し、天国へ旅立った。いっぱい泣いた。ずっとおばあちゃんの思い出が私の心にへばりつき、はなれない。ずっと私の中でおばあちゃんの笑顔が見える。その笑顔がうずをまいて、外に出ようとする。私は泣きやめなかった。なみだをのみこめない。のどが苦しい。この経験は今までで一番最悪の出来事だった。
でもおばあちゃんの死は、自分を変えてくれた。小学生前までは相手に意見を言えずにいて、ちょっといじられていた。しかし今ではすっかり、自分の思いを積極的に言うことができる。そして、大福で学んだ、相手を気づかう心も学んだ。今、考えると大福のエピソードはとてもおもしろい。苦笑いしながら大福を食べる自分を思い出すと、つい笑ってしまう。
そんな、おもしろいおばあちゃん、空でも私を見守っていてね。