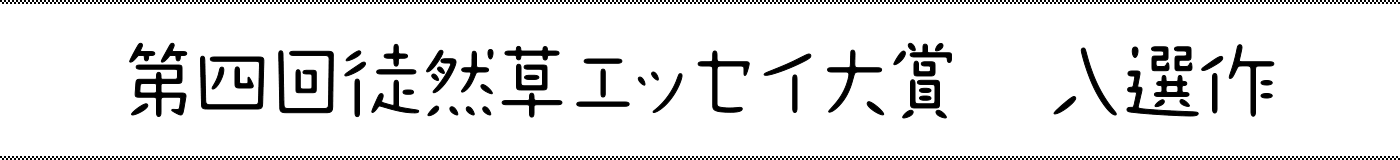
これは、私が小学校六年の頃、母と妹と三人で駅前のスーパーに行ったときの話だ。
当時小学校三年だった妹は、ぱっと見ればまだ少し幼さの残る女の子だ。でも、違う。妹は知的障がいだった。現代医学では治療法のない脳の病気だ。言葉は母音しか話さず、意味のあるしっかりとした単語を話さない。そんな妹と毎日共に過ごす日々だ。
そんなある日のこと。夏も近づき、少し蒸し暑かったが雲一つない青空が広がっていた。その日は学校が休みだったので、家でボーッとしているのもなんだからと駅前のスーパーに買い物に行くことにした。家からスーパーまでは歩いて二十分ほどかかる。妹は嬉しそうに帽子をかぶり、大きく名前の書いてある水筒をかけて手をぶんぶん上下に振っている。「嬉しい」のサインだ。
「行くよー」。母の一声で家を出て、坂を下っていった。家からスーパーまでは延々と続く下り坂だ。しかし、妹はぐんぐん進んでいく。つないでいる手を放しては走っていくので少し心配だ。
「ああっ、ちょっと!」
母が大声でそう言っても、妹は止まらない。二人で急いで追いかけて、やっと追いついた。
「手、放しちゃだめでしょっ」
そう母が言っても、妹は笑ってる。それを見ていたら、なんだか笑いがこみ上げてきて、みんなで大笑いした。「楽しい」。そう思った。
そうこうしていると、スーパーに着いた。割と大きめのスーパーである。妹は店内に入ったとたん、走りだした。スーパーでは、母だけ別行動をして、買いたいものがあったら母の所へ持って行き、カートに入れるというのが、私の家の買い物方法である。私は突然走り出した妹を捕まえて、野菜、肉、魚、菓子など、スーパーを見てまわり、最後に母が並んでいるレジに向かった。また妹が急に走りだした。すると、婦人服売り場から出てきた四十代くらいの主婦にぶつかった。私が謝ると主婦が「どうしたの?」と聞くので、知的障がいのことを話した。
「かわいそうにね。知的障がいだなんて」
私は一気に胸がいっぱいになった。かわいそうなんじゃなくて、苦手なことがあるだけなのに。怒りよりも悲しみのほうが大きかった。母は何も言わなかった。聞こえなかったのかもしれない。気がつくと、その主婦はいなくなっていた。
世界は、変わらなくてはならない。障害のある人に「かわいそうにね」なんて言わない世界に。人には、苦手なことが必ずある。だから、人は支え合っている。それぞれの得意なことで、他の人の苦手なことを支え補いながらまるで一つの輪のように生きていかねばならない。この一つの輪の中に、障がいがある人も、ない人もすべての人が平等に入らなければ、この世界は成り立たなくなる。そのために必要なのは、言葉にする「勇気」と行動しようとする「心」である。