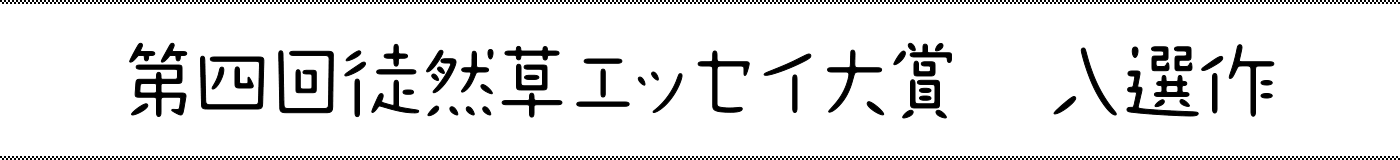
「転石苔むさず」という言葉があるが、石を人生に例えるなら転がり方も人様々だ。転がる距離、速度、原因等々。私の場合は単に逃げだったのかもしれない。転職を重ねても続かず、肩パット入りのOLスーツも着こなせず、三十歳を迎える一九九三年の正月、当時、趣味で通っていた語学学校が主催した半年間の語学留学に参加した。行く先はモスクワ。ロシアの大学が日本人向けに開講したロシア語セミナーである。
空港に迎えに来たロシア人教師のワゴン車でモスクワの寮に向かったのはすでに深夜だった。クレムリンの塔の上に闇の中、燦然と輝く五角形の赤い星が見えた。それがルビーで造られていると聞いて、異国に来たことを実感した。セミナー参加者は六人。ほぼ二十代のロシア語基礎知識のある若者たちだったが、初心者の私は授業についてゆくのがやっとだった。
なぜロシア語なのか。ソ連が崩壊した過渡期のロシアは、「これから経済的に発展し、ロシア語の需要は必ず増えるはず」と友人に言われた。「そうかもしれないな」と山師のような動機と未知の世界への好奇心――その程度の目的意識で私はモスクワにやってきたのだ。
そして、「ロシア語通訳になる」という目標を定めた。しかし、現実は厳しい。「おまえは何故上手くならないのだ?」とロシア語教師たちの罵倒にもへこたれずセミナーに通った。半年が経っても通訳レベルになるはずもなく、ロシア語教師の斡旋でホームステイしながら個人授業で勉強を続けることにした。
一九九三年のロシアは混乱していた。貿易の自由化で物価も自由変動。国内生産の落ち込みで物資は不足。ルーブルの価値は暴落し人々はドルに群がった。流通機構の破綻により店に商品は無く常に長い行列ができていた。しかし市場にはロシア中から商人が集まり、高値だが物があふれていた。人々は市場の入り口や路上で無許可ではあるが持ち寄った品物を売っていた。やかん、靴下、ペット、自家製ジャム等なんでもあり。太平洋戦争終了後の闇市はかくもあったであろう、と思われる風景だった。
私はモスクワの東部、七〇歳の年金生活者マリアさんの住むアパートの一室を借りて週四日の個人レッスンに通うことになった。下宿代がひと月五〇ドル、授業料が一日三時間で五ドル。申し訳ない程の破格で当時は暮らすことができた。目標はロシア語通訳――しかしその道のりは遠い。世情不安定な町で、ひっそりと勉学に励んだが、それ以外の時間は生きるための生活物資の調達に割かねばならなかった。
糖尿病のマリアさんに頼まれて、彼女の食糧も買い出しに行くのが日課だった。キャベツ一個、人参一キロと頭の中で買い物リストをロシア語で復唱しながら近くの商店で列に並んだ。卵は路上で手売りを二〇個。フルーツは駅前市場でカフカス人からオレンジやザクロを。マリアさんの持病に杏が効くらしいからついでに買って来る。
一年もたつと、マリアさんの頼みで近くに住む病気の妹にパンを届けることになり、妹の住むアパートにちょくちょく通うことになった。彼女たちは糖尿病の家系で妹の息子は脚を切断して働けないという。
そんな私をロシア語教師たちは「ドーブリー」だと言った。ドーブリーは良いという意味だ。「お前は語学の才能はイマイチだが」とつけ加えて言った。私が日々の出来事をレッスンの一環で一生懸命に話すと彼らは、お前は「ベショーリー」なやつだと微笑んだ。ベショーリー=陽気。陽気な善人――まるでロシア民話の登場人物ではないか。日本で私をそのように評する人は誰もいなかった。
マリアさんは私に簡単なロシア料理を教えてくれた。キャベツと鮭缶のスープ。ビーツをゆでて賽の目に切りキュウリ等野菜とマヨネーズであえたサラダ。蕎麦の実を蒸して牛乳と混ぜて食べるお粥。実験と称して一緒に料理をし、自家製のピクルスやベリーのジャムをお裾分けしてくれた。そんな生活は楽しかったが、ロシア語通訳が目標だった私は三年後に帰国した。
帰国して四年目に私は目標のロシア語通訳の国家資格を得ることができたが、それで生計を立てることはできなかった。ロシア語通訳にもなれず、ロシア語ビジネスも実現しなかったが、気がつけば今の私を支えてくれているのは、ロシア人達に気づかされた「ドーブリーでベショーリーな私」なのである。
「陽気で善良な人間」であること。それは秘かな自信になった。転がる石は目的地とは遠い離れた場所で意外な着地点を見つけたのだ。
今、私は老人施設で調理の仕事をしている。モスクワでマリアさんと料理をして以来、料理に興味が湧いてきたのだ。私という石はさらに転がり続けるのだろうが、彼らが与えてくれた言葉は今も私の心に生きている。