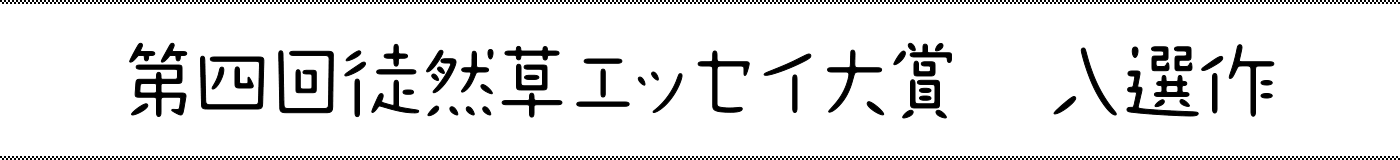
そのにわとりの話を聞いたのは一九七〇年のことで、当時私は小学一年生だった。出雲地方を山へ山へ――中学教員だった父の赴任地は、橋のかかった大きな川がキラリ、キラリと光りながら流れる村だった。川は水面のあちこちに、丸みを帯びたり荒く削れた面をもったりの大小さまざまな岩を覗かせ、岩々の周りには濃い緑の草が噴き出すようにたっぷりと、丈高く生えている。流れが変わる場所では輝く水の泡が幾つも幾つも生まれて弾け、黒々と濡れた岩もざわめくくさむらも、全てが強い光の粒をいっぱいに浴びていた。
その川の近くに小学校はあった。早生まれの私は体が小さくて、号令に遅れがちな子どもだった。担任の先生は穏やかで、なかなか前を向けない私を見守り、皆が揃うとゆっくり目を細めほほえまれる。真似して目を細めると、いつも私の心は落ち着いた。
その日、午後の授業の始めに先生は「お話」をされた。清掃が終わった教室は木枠の窓が開け放たれ、山からの風が床の水拭きの跡を静かに乾かしている。
「大きなコンクールで――」と先生は言われた。にわとりの絵を描いて賞をもらった子がいるのです。絵のなかのにわとりには、足が三本ありました。三本の足を描いたところが良くて、賞をもらったのだそうですよ。
私は不思議に思った。ついこの前、テレビニュースで大人たちが「近ごろの子どもは」と、呆れた様子で話しているのをみたばかりだったからだ。近ごろの子どもは全くどうなっているのか。鳥の絵を描かせると、平気で足を四本描いたりしている――。
三本なんて、四本よりもっと変じゃないか、と私は思った。絵を描いても賞などもらったことのない私には、納得できない気持ちが残った。その頃妹が次々生まれ、親の目の届かなかった私は自由だった。村の裏山へ続く小道を一人、暗く見えるほどに濃く繁る緑のなか、奥へ奥へと歩いた。風がざわざわ吹いている。この道は、どこに続くのだろう……。
時が経ち、県内の大学を卒業した私は小学校教員になった。そして受けもちの児童たちが描く生き生きとした、思ってもみないような大胆な絵の数々を前に、かつて聞いた不思議な児童画のにわとりに思いを馳せることとなった。そう、三本の足をもつにわとりに――。
教員生活は二年間しか続かず、退職した私はフェリーに乗って一人、知り合いのいない遠い沖縄に渡った。仕事を見つけ、職場で出会った人と交際が始まり、結婚が決まった。
婚約中、二人でドライブをしていて飛行機の話題になった。のどかな春の日、訓練の戦闘機が凄まじい音をたて上空を裂いていく。
「初めて飛行機に乗ったのいつですか?」
轟音の止み間に私は聞いた。私の場合は小学一年生の夏休み、一九七〇年大阪万博のときだったのだが、
「俺も万博でしたね」と彼は言った。「万博の絵のコンクールで賞をもらって、授賞式に招待されたんですよ。当時沖縄は日本に復帰する前だったから、パスポートをもって行きましたね。授賞式で岡本太郎と握手しました」
「えっ、すごい。因みにどんな絵を描いたんですか?」
何ということもなく、私がそう聞くと、
「にわとりの絵だったんですが――」と彼は答えた。その頃私たちは職場の延長でプライベートでも敬語が抜けなかったのだが、彼の口調がそのときだけ不意に、沖縄の少年のものに変わったことを印象深く覚えている。
「にわとりの絵だったんですが――何でかわからないんだけどよ、足を三本描いてしまった」
今、スマホのアルバムを開くと夫は変わらぬ笑顔で、穏やかに私を見返してくる。二十五年の結婚生活だった。遺影に使った写真は五十一歳、脳出血で急死する三カ月前に撮影したものだ。夫は初夏の沖縄の海をバックに、何か面白いことでもしでかしそうな、いたずら好きだったという子ども時代を思わせるような顔でにんまり笑っている。
「この感じ、お父さんらしいから」と娘、息子のチョイスである。
死後になって、夫の実家から「万国博覧会世界児童画展特選」の賞状が出てきた。私と娘、息子は大阪の万博記念公園を訪れた。事務所の方が準備してくださった資料コピーには当時の入賞者として夫の名前、そして題名『にわとり』。絵の行方はわかっていない。
その後私は故郷に戻り、父と暮らした。二年が過ぎた今年の春、父の部屋のストーブから出火して家は全焼、夫の賞状も燃えた。
私は想像する。一九七〇年の万博会場で、一人の少年のもとを抜け出し、歩き始めたにわとりのことを。誰にも見つからず、五十年間歩き続けているにわとりのことを――。
まだ何かが起こる。生きるということは、変化するということだ。私は今も、三本足のにわとりを探している。