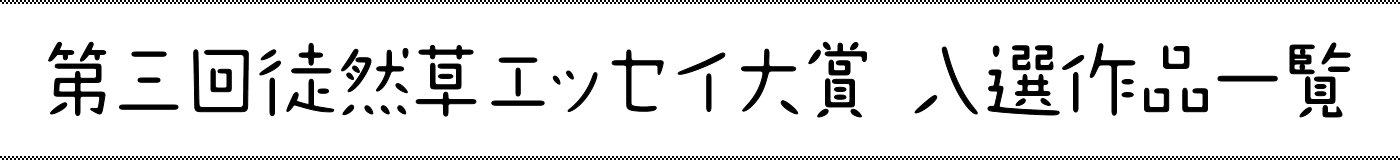
十一年前の三月末日、退職されたA校長が私の校長昇任の祝いとして「湯飲み茶碗」を持って来校された。開口一番「どうして学校には校長室があるのか?」。私は返答に困ってしまった。明日は校長職として初任地(福島県いわき市)へ行くのに未だに昇任試験を受けているようだった。単純に「校長が執務する場所だから校長室」だと思ったが、A校長の質問には別な意味があると思い、「明日から校長室で考えます」と曖昧な返答をした。
翌日から「校長室の存在」について真剣に向き合うことはなかったが、その理由を発見する出来事は突然に訪れた。それは、校長として三年目、約八年前に起きた東日本大震災である。あの時、一瞬にして残酷なまでに多くの命を奪われ、故郷の風景は消滅したが、悲しみや怒り、不安等という負の感情にずっと埋もれている場合ではなかった。特に「希望」だけは失うわけにはいかなかった。子どもや保護者、地域に「前に進もう」と支えていくことが学校に与えられた役割だった。
三月中旬、余震の続く間、夜は避難者の車が校庭に所狭しと並んだ。当時、私は避難者等の電話対応やトイレの案内、人数確認等でアパートに帰宅するのが早いときでも夜の十時過ぎだった。学校を解錠したある朝、春の光が射し込む校長室の窓に一通の手紙がガムテープで貼ってあった。風で飛ばされないように余震で落ちないようにガムテープで貼ったのだろうか。手紙には、「校長先生、私達は校長室に灯りが点いていると、とても安心します。困ったら、校長先生にすぐ言えば何とかしてくれると思っているからです。でも、聞くところによると、校長先生は単身赴任と聞きました。実家には若い奥さんと小学生の女の子がいると聞きました。週末には自宅に帰ってください。学校は私達で守ります。なお、子ども達が登校する七時前には校庭から車は出します。ごみは持ち帰ります。今日も子ども達を頼みます」
と、丁寧な文字で書かれていた。
「そうか、家族を守るために今この瞬間を生きている避難者の方、不安におびえながらも明日を待っている方の思いが集中する場所が校長室だったのか。そして、校長室の灯りというのは不安を消し心を穏やかにする光なのか」と初めて「校長室の存在」を考えることができた。校長室は単に目の前にある諸々の仕事を片付けるためだけの場所ではないことを地域の方から教えられた。振り返ると、三年前の今頃は校長に昇進することで人生のゴールに達したかのように錯覚していたのではないだろうか。私にできることは何か。このことを知る機会はすぐに訪れた。
三月末から夏休みまでの校長室のソファーには毎日のように転出・転入する児童が親に挟まれながら座っていた。校長室から校門を出て新しい土地へと旅立つ家族、校長室からこの新しい学校の教室に入っていく児童が私の目の前にいた。どの家族にも共通していたのは身も心も「希望」という一本のネジを抜いたら壊れそうな状態だった。だからこそ支える、それは子ども達に生きていくことの嬉しさを伝えることだということを先生方同士で確認しあった。
校長室で聞く子どもの「さようなら」は淋しく切なかった。転学していく二年生の男の子が昇降口で小さい背中を丸めて新しい靴の紐を何度も結び直していた。やっと紐が結べてこちらを向いたとき、大きい瞳から涙が流れていた。そして、「僕、この学校がいい」と言っていた。
消え入りそうな声での「こんにちは」はこの上なく愛おしく感じた。この学校にたどり着くまで、肉親を失った子、宝物のぬいぐるみが濁流の中に飲み込まれていく姿を目にした子がいた。そして、多くの人の涙を肌に受け、悲しみの声を聞いてきたのだ。それでも健気に挨拶しようとする姿に「先生達は〇〇さんの応援団です」と声をかけあった。ただし、「頑張れ」とは言わなかった。
わずかな時間ではあったが、多くの出会いと別れが校長室で起きていた。しかし、その出会いと別れも学校と家族が「希望」を確認し共有する不可欠な「めぐりあい」だった。
ある先生から「校長室のドアは駅の改札口みたいですね」と言われた。今までの多くの家族が前に進もうと一歩踏み出す場面を思い起こすと、校長室は学校の駅であることを知った。そして、学校を始発点として児童や家族のための希望のレールを限りなく延ばしていくことも。それが学校の役目である。
さらに、もう一つの発見は、震災後に亡くなられたA校長の厳しさの裏にある私に対する奥深い優しさだ。あの地震の中でも湯飲み茶椀は割れなかった。
A校長は、私のあのときの姿をずっと遠くから見守っていたのだと確信している。