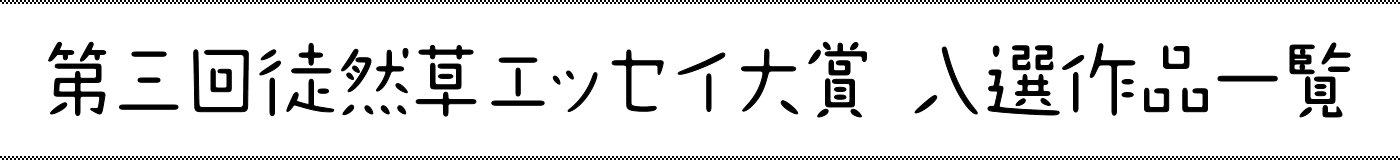
「それは捨てたらいけんよ。宝物なんじゃ」
薬剤師の国家試験に合格し、京都の大学寮から出て一人暮らしを始める、娘の引越しを手伝いに行った折のこと。
私が持ち上げたみかん箱を見て声を強めた。
そっと降ろし、段ボールの蓋を開けると、色とりどりの大小の紙がぎっしり入っている。
「これな、保育園の頃からもらったお母さんからの手紙なんよ。もうボロボロじゃけど」
娘は箱ににじり寄り、一枚を取り出した。
「辛い時や寂しい時、読み返してきたんよ」
娘が手にしたのは、チラシ裏の白い面に、黒マジックで書いた近況報告や励ましだった。
「宅配で野菜やお菓子を六年間、たびたび送ってくれたよな。荷物の一番上にデンとチラシとかの手紙を乗せてくれてたじゃろ。中身より、手書きの手紙の方がかったんよ」
娘は私に、表彰状のようにバッと掲げた。「急いで書いた字か、落ち着いた字か、文字の大きさや強さ、配列で、あぁお母さん、今、仕事で忙しいんやなと、疲れて丸まった背中や食卓で書く姿まで見えた気がしたんじゃ」と微笑み、「一番心に残った手紙はな」と、『最後の一秒まで諦めるな』と、黒い太マジックで力強く書いた、紙からはみ出すような一文だけの手紙を私に向けた。
「お母さんの気持ちが、紙から飛び出してくるようじゃった。文字の勢いに圧倒されて」
そのチラシの四隅に小さな穴が開いている。恐らく、壁に貼って毎日眺めていたのだろう。
「手書きのメッセージって、味わいあるなぁ。相手の表情や体温までが伝わってくるもんな。立派な便箋でなくても、引きちぎった紙でも、一枚の紙に、送り手がそこにいるように響いてくるんよ。相手への想いを込めて生まれる、世界で一つの手書き文字じゃからかなぁ」
娘が丁寧に折りたたんで、再びダンボールにしまうのを見て、大学時代、みんなの前で一人だけ指導されたことを思い出した。
「心で書け。印刷したように綺麗に書こうと思うな。人の気持ちは一律ではないだろ」
入部した書道部は仮名専門、老齢の指導書家は、歯に衣着せぬ勢いで言葉を投げかける。
「手紙で想いを交わしていた時代に思いを馳せよ。恋しさや嬉しさ、届かぬ胸中の恨めしさ、憎しみ。人間のドロドロした部分や清々しさ、優しさなどが複合し文字は生まれる」
書家は、つい見栄え良く美しく書こうとする私に、普段の手紙でも、どう自分を表現するかで相手に伝わる熱量が変わると説いた。
「悪筆でいい。曲がりくねった癖字でいい。一枚の紙の上に文字を置くことは、息遣いを始めさせること。紙の上で生き物になった文字が、思い余って踊っても、暴れても、肥大しても、震えたっていい。君が理想とするなら、規則正しく行進させてもいい」
幼稚園児の頃から母に、「罫線やマス目からはみ出さず、お手本通りの文字を丸ごと写すように書きなさい」と言われ、杓子定規から脱皮できない私に、「手書きの手紙はな、単に文字の美醜や筆圧という書き記された部分だけが妙味ではないんじゃ。相手を想い、次の言葉、続く文章を考える息継ぎに生まれる文字と文字の間合い、行間や余白にも、手書きの醍醐味がある」と続ける。部室を見回しながら、しわがれた声で、「読み終えた手紙を折りたたんでも、紙から相手の声や息遣い、体温までが立ち昇るように感じた経験があるじゃろ」と、全身から汗が吹き出し赤面する私に問うた。
「手書きの言葉と紙面の余白。二大要素が、命を吹き込んだメッセージとなり、読み手の心に鐘のような余韻、味わいを生むからな」
俯いたまま何度も頷く私の机の横で、「手書きの手紙には、その送り手にしかできない余白と余韻があるからこそ、胸の深い所へ響くもんじゃ。書も、そうあってほしい」と机をトンと叩き、「私も修行中」と笑った。
その日以来、肩の力が抜けたように、手紙を書くのも、仮名書道も苦にならなくなった。
溢れる想いの時は、文字は情熱のままにびっしりと並ぶ様相になり、動揺の時は、乱れもかすれも生じる。どの顔も間違いなく私だ。
余白も余韻も、私の化身の魅力と発見した。
「私な、夢があるんよ」
ジャージ姿の娘が居住まいを正した。
「小さい頃、お母さんが家で作った野菜やお土産を近所に分けてあげる時、必ずメッセージを私に書かせたじゃろ。すごく嫌だった」
と口をとがらせた後、肩をすくめて見せた。
「でもな、高校の時、近所のおばあさんから、嬉しくて今も手紙があるよと言われたんよ」と目を大きくし、「患者さんに、直筆で手紙を書いて、励ましたいんよ。下手な字じゃけど、伝えたい」と照れたように笑うと、「お母さんからの手紙パワーのおかげかな」と娘なりの発見に満悦な色で箱を抱きしめた。