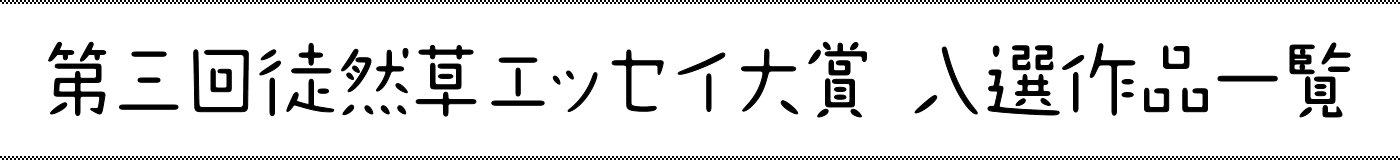
初秋の頃、夜が明けるまで月を眺めては、歩きまわったことがある。美しい満月の晩だった。月光だけを頼りに散歩したのは、いつ以来のことだろう。漆黒の闇の奥から、鈴虫の鳴声だけが響きわたり、心は我を忘れて酔いしれた。しかし、民家の灯が遠く彼方にちらつき、ふと我に返ると、寄る辺のない絶望的な孤独が、押し寄せてくるのである。
長年、勤めた会社を解雇されて、苦悶と放浪の末にたどり着いた田舎町だった。日本海を見下ろすこの漁村で、しばらく、間暇をとることにしている。
無職となったいま、社会的には何者でもない。無念とともに諦念が湧きたち、世の無常に想いを馳せる。若き日から、少なからぬ野望を抱き、数限りない夢を見ては努力を重ねた。しかし、それが、こともなげに、ぷつりと切れた。
思えば、会社時代は、蟻のように、奔走して、毎日をやり過ごした。感性を押し殺していたといってもいい。身体の続く限り、結果を追い求めた。疲労はしたが、疑問を抱くことはなかった。会社にしがみ付くことで精一杯だったからだ。一線を退いて、振り向けば、まるで夢幻のなかで、足掻いていただけなのかもしれない。暗く沈んだ日本海の水平線が、遠くにぼやけた。幻想からふいに目醒めた虚しさで、胸が詰まりそうだった。
昨晩からのしとしと雨は、今朝になっても止むことはなく、それどころか秋の冷気が肌身に沁み入る時節となった。外出が鬱陶しいのは言うまでもなかったが、しかし、それでもと気持ちを奮い立たせて、雨靴を履いた。
緩やかではあるが、滑りやすい坂道を登りつめると、古ぼけた寺があった。辺り一面、苔むして、お世辞にも手入れが行き届いているとは言えない有様だったが、その風情に何故か心を惹かれた。山門を抜け、本堂に至ると、初老の男性がにこやかに、こちらを眺めている。住職だろうか。坊主頭に、毛糸帽がよく似合った。
何気無く会釈をすると、のんびりとした足取りで、こちらに近づいて来る。なにやら話しかけられたが、最初は軽く笑顔で受け流した。それでも、なんやかんやと聞いてくるので、次第に会話らしきものが成立しはじめる。
聞けば、住職も、その昔は、東京で仕事をしていたことがあったそうだ。いわゆる都落ちだよ、と言って、楽しそうに笑っていたが、その話題に飛び乗る気には、到底なれなかった。切り返す言葉が見当たらず、樹齢数百年はあるだろう、鬱蒼と生い茂る大樹を眺めていると、その様子を、確かな観察力で見つめる眼差しがつよく意識された。
「お釈迦さんを知っていますか」
唐突な質問だった。知らないわけではないが、知っているわけでもない。そのような類のことを答えると、住職は、雨上がりの空を見上げて、けらけら笑った。
立ち話もなんだから、と手招きで、母屋の縁側に招き入れられた。こちらとて、急ぎの身の上ではない。断る理由も見当たらず、住職のあとを追った。気さくな好意が、むしろ有難かった。
縁側からなんとは無しに、和室を覗くと、溢れかえった書籍の山が、目に止まった。古書が多いのか、そのほとんどが黄ばんで草臥れている。
「老人の暇つぶしですよ」と、住職が目を細めて言った。
「特に良寛さんが好きでねえ」
良寛とは、記憶のどこかで聞いたことのある名前だったが、生きた時代も場所も皆目、見当がつかない。それを見通してのことか、住職は、ゆっくりと解説を始めた。
江戸時代も後期、この漁村からほど近い、新潟県出雲崎に生まれた良寛は、長年、諸国を放浪し遊行した僧侶らしい。しかし生涯にわたって寺を持つことはなく、托鉢を旨とする、清貧の乞食僧だった。有名な逸話としては、子どもたちと手毬で遊んだことが知られるが、漢詩や和歌にも習熟していたようだ。法華讃といった法華経を称えた漢詩もある。
住職は、ひととおり話し終えると、この言葉をご覧なさい、と言って、一冊の本を手渡してきた。
災難に逢う時節には、災難に逢うがよく候。死ぬ時節には、死ぬがよく候。これはこれ災難をのがるる妙法にて候。
住職は、言った。「何か障りがあると、その障りを克服しようともがいたり、逆に打ち砕かれて落胆するものだが、悪足掻きはいけません。むしろ腹を据えて、いま、ここを精一杯に生きたいものです。良寛さんもすべてを捨て去る世捨て人になってはじめて、融通無碍の境地に遊び、月や花を愛でるゆとりも生まれたようです」
張り詰めていた背中の緊張が、ふいに緩み始めたのが、わかった。解雇を言い渡された日から、一度も緩んだことのない緊張だった。心の奥底で、他者を憎み、恨み、妬みもした。しかし、それで現実が変わるわけではない。無駄な心の労力だった。
一息ついて、もう一度、読み返してみる。「死ぬ時節には、死ぬがよく候」。寺の裏手を流れる滝の音が、思いがけず、新鮮な響きを上げた。
急激に胸が熱くなり、涙が頬をつたった。差し出された手拭いを、私は、思う存分に濡らした。