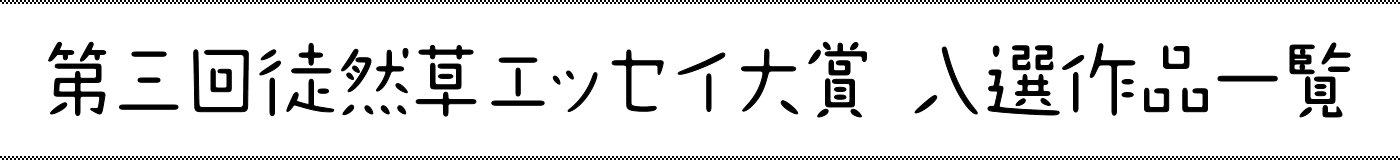
僕は昔から勘の鋭い子どもだった。
包丁の音で母ちゃんの機嫌がわかったり、父ちゃんの玄関を閉める音でパチンコか仕事なのかがわかった。
そんな僕は四人兄弟で、いつもおかずはきっちり四等分だった。 ハンバーグのときは、大きいだの小さいだのでいつもケンカになった。
兄弟の中でも三番目とあって僕がハンバーグをもっと食べるには弟のをとるしかなかった。いつだって僕のケンカ相手は弟だった。そのたび小さい弟は母に泣きついて、そのあと僕がお尻を叩かれた。だけど次の日にはそんな痛みなんかすっかり忘れてまたケンカをした。弟が悪いときだってもちろんあった。だけど怒られるのはいつも僕。年下で甘え上手な弟は僕にとって疎ましい存在だった。
そんな僕が五年生のときだった。理科の授業で「ヒトの誕生」を学んだ。教室に助産師さんを招いてお話を聞いた。「人の遺伝は耳に表れることが多い」
普段、真面目に先生の話を聞かない僕もそこだけ切り取るように覚えていた。
みんなが集まる夕食どき、昼間のことを思い出した。ふと家族の耳を見れば父も母も兄もみんな福耳だった。しかも餃子みたいに分厚い。これはきっと家系なのだろう。僕も自分の耳をさわってそう思った。だけど弟だけどう見ても皆とはちがった。ペラペラの、いわゆる平耳というやつだった。僕はその紙ペラみたいな耳をじっと見た。
「おい、なんだよ」
「なんかちがう」
「なにがだよ」
「耳のかたちが俺らとちがう。もしかしてお前だけ拾われたんじゃねえの」
とっさに父ちゃんはテレビの音量を上げて、兄は二階へかけあがった。母の様子は覚えていない。ただ僕がまずいことを言ったのはその空気からすぐにわかった。
結局、十時過ぎに母が僕の部屋にきた。どんな言葉だったかはあまり覚えていないが、弟は僕らと血のつながりがないということだった。言葉がなかった。
それから何事もなかったように時が過ぎた。相変わらず僕と弟はケンカが絶えなかった。その日は僕が弟の財布から五百円抜いたのがバレた。うちの小遣いはみんな千円と決まっていた。だけどそれでは到底足りなかった。僕は母に交渉するよりも弟から盗んだ方が早いことをわかっていた。だけど弟は僕のことを母に告げ口した。
母ちゃんが出てきて、かばうように僕を責めた。そのうしろで舌を出すようにしている弟が目についた。頭に血がのぼって僕は口を滑らせた。
「なんだよ。お前の母ちゃんじゃないくせに」
場が凍りついた。しまったと思った時にはもう遅かった。母ちゃんがすぐさま平手で僕を殴った。頬を叩かれたのは初めてだった。痛い。明らかにお尻のときよりも痛いじゃないか。お尻と頬ではこんなに痛みがちがうものなのか。僕は絶句した。それから母ちゃんは言った。
「何言ってんだい。みんな、私の子だよ。バカなこと、言うんじゃないよ」
「………………」
「みんな、母ちゃんの子なんだよ」
それはどこか自分に言い聞かせているようにも見えた。分け隔てなく育てることへのプレッシャーを人知れず感じていたのかもしれない。
僕は叩かれた痛みより、母ちゃんが弟を抱きしめて、その場でわんわん泣いている姿が苦しかった。はじめて見た母の涙。顔が涙と鼻水でぐちゃぐちゃだった。 だけど抱きしめるその強さから血の繋がりを超えた母の愛がはっきりわかった。
母は「里親」ではなく「親」で、弟は「里子」ではなく「子」だったんだ。
「みんな、母ちゃんの子」
その「みんな」という言葉に母のただならぬ愛情を感じた。今になってみれば僕を思いきり殴った手さえも僕への愛情なんだと思える。
勘の鋭い僕ではあるが、頬を殴られてやっとわかったことがある。
母の愛は、平等でも分けられるものでもなく、全力なんだって。