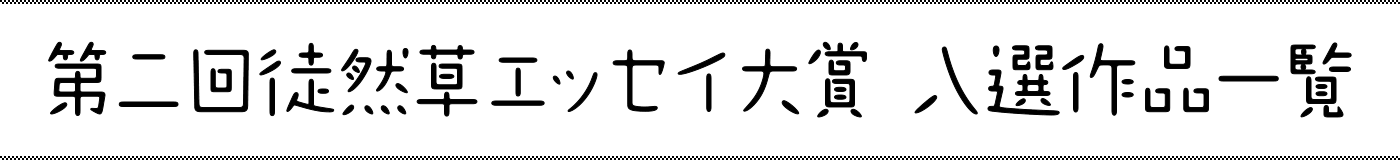
ピヨ丸とチビ丸に出会ったのは小学五年生の十月だった。当時お祭りの定番だったひよこ釣り屋台に彼らはいた。両親がひよこを飼うことをあっさり許可したのは、どうせ長くは生きられないと思っていたからだと、随分後になってから聞いた。
両親の予想に反し、ひよこたちはすくすくと順調に育った。愛らしいルックスと人懐っこさで、瞬く間に家族のアイドルになった。好物は大根の葉を刻んだもので、小さなくちばしでチョンチョンとついばむ姿は私たちのハートをもついばんだ。寝ていると、枕と首のすき間に体をねじ込んでくる。温かいのだろう、ちょっと寝返りを打つと潰れてしまいそうで寝られなかった。
十二月になると、ひよこたちに異変が出始めた。黄色い産毛が白い羽に生え換わりだしたのだ。私は青ざめた。通っている小学校で飼育している白いニワトリは皆馬鹿でかくて凶暴で、まるで番長だ。この子達もあんな風になってしまうのか。私は小ぶりで茶色い、温厚なニワトリに成長するものだとばかり思っていたので愕然とした。
年明けには真っ白な羽に生え換わり、立派なニワトリ風を吹かせるようになっていた。ピヨピヨではなく一丁前にコッコッと鳴く。エサを持って行くと「はやくしろよ」と怖い目でつついてくる。これが地味に痛い。私の予感は的中しつつあった。絶対に番長になる。この頃から、家族の間で不安の声が上がり始めていた。日に日に存在感を増す彼らに恐れを抱き始めていたのだ。
三月になり、父の仕事の都合で引っ越すことになった。今は庭付き一軒家だが、次は違う。家族であるピヨ丸とチビ丸を、連れていくことはできないと言われた。為す術もなく、最終的には納得するしかなかった。
里親を見つけるべくあちこちあたってみたが、卵も産まない好戦的なニワトリを欲しいという変わり者はいなかった。そんな時、近所のおばさんが母に、何やら吹き込んでいるではないか。「ニワトリを持っていったら一羽数百円で肉にしてもらえるところがあるよ」。私は耳を疑った。恐ろしい話を聞いてしまい、足がガクガクと震えた。
その後のことはぼんやりとしか覚えていない。気がつくと、ピヨ丸とチビ丸を両腕でそれぞれ抱きかかえ、駆け出していた。行き先は数キロ離れた、周囲からは『ニワトリの館』と呼ばれているお屋敷だ。グラウンドのような広い庭に、いろんな種類の大小様々なニワトリ達が放し飼いにされている。数日前、飼い主にニワトリを引き取ってほしいとお願いしたが、断られてしまった。館に着くや否や、塀の上から必死に羽をバタつかせて抵抗する彼らを、夢中で庭に放り投げた。二羽増えたところでばれっこない。「ごめんな」とだけ言い、すぐに踵を返して逃げた。
とぼとぼ家に帰ると、どういうわけか既にばれていた。こっぴどく叱られ、すぐにまた母と一緒に謝りに行くことになった。どうして私がこんな暴挙にでたのかを聞いた母は、吹き出して「そんなことするわけないたい」と笑った。
でも、この暴挙は無駄ではなかった。ニワトリの館であの荒くれ者達を引き取ってくれることになったのだ。飼い主の気が変わらないうちにと、私と母はそそくさと館を後にした。庭の隅っこで寄り添いながら震えている二羽が見えた。私はまた「ごめんな」と小さな声で言った。
辺りが暗くなる頃、ようやく帰宅した。もう不要になったニワトリ小屋には、食べかけの大根の葉や羽が散らかっている。もうここには戻ってこない。ピヨ丸とチビ丸は新しい住み家へと旅立ってしまった。そして数日後、私たちも新生活へと旅立った。
それから一年、私は再び館の前に立っていた。相変わらずたくさんのニワトリが庭中を駆け巡っている。すぐに見つけた。白くて馬鹿でかいのが二羽連れだって、悠然と歩いている。やっぱり番長になっている。もう、私のこと覚えてないんだろうな。やっと安心した。