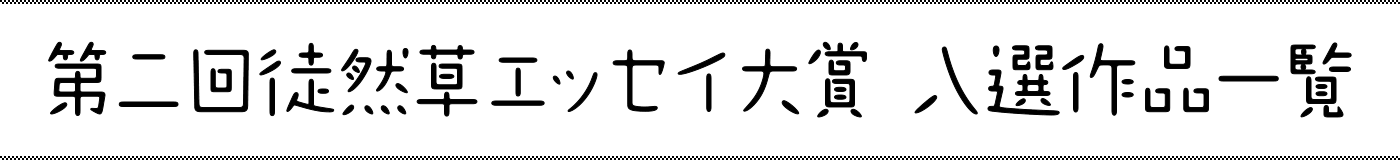
「お若い先生には、私の悔しい気持ちなんか分かりませんよ」
吐き捨てるように放った瞬間、両太腿に置いた拳は、内側の肉に爪跡が残るほど力が入った。診察室に気まずい空気が流れる。
「おそらく、今までのようには走れません」
先ほど、男性医師が私から目を反らせて告げた言葉が、胸の中で旋回する。
「重い物は持たない、階段は使わずエスカレーターやエレベーターで、ヒールの靴は履かない、スポーツはもちろん、スクワットなど膝の屈伸運動は厳禁、極力歩かない」次々に出された指示も、頭を巡る。
二十九歳の私の娘と同年代に映る整形外科医は、眼鏡の奥の細い目を見開き、反抗心むき出しの私に、ゆっくりと言った。
「膝の半月板は一度裂けると、二度と元には戻りません。これ以上悪化しないよう、指示は守ってもらわないと。歩けなくなります」
驚きと悲しさとがごちゃ混ぜになり、うなだれたままの私に看護師が肩を貸し、廊下へ連れ出した。左膝に巻かれた、ごつい固定ベルトは、膝の曲がりを阻害し歩きづらい。
左膝に異常を覚えたのは、二ヶ月ほど前だった。それでも、二十年間続けている毎朝の山へのウォーキング四キロの道程と、週一回のアクアビクスやジムは休まず出かけていた。
単なる疲れと思っていた膝周りの鈍痛は、一向に治らない。ウォーキング仲間たちから、「膝の水が原因よ。抜いてもらえばたちまち楽よ」と勧められ、気軽に受けた診察だった。
思いがけない診断結果に、帰宅して泣いた。
主婦の傍ら、司会の仕事をする際に履くヒールの高い靴を下駄箱から次々に引き摺り出し、「もう、履けないんだ!」と泣き叫びながら玄関タイルに投げつけた。ヒールは欠け、打ちつけられるたび悲鳴を上げてパンプスは転がった。ウォーキングのシャツもズボンも帽子も、日よけ手袋も、「見たくない」と、ゴミ袋に押し込み、アクアビクスの水着も、ジム着も「着る日は来ない」と全て捨てた。
くすぶる気持ちは、外にも向けられた。
左足を引きずるように生活する私の目に、颯爽と歩く女性の姿は、羨ましさや嫉妬以外の何物でもなかった。スローテンポでしか歩けない私を「邪魔だ」とばかり、舌打ちや、体を当てたりして行く人に対しての苛立ち。
スーパーに行けば、カートにすがらなければ、ろくろく買い物もできなくなった自分が店の鏡に映るたび、スポーツに明け暮れた頃が蘇る。唇を噛み締め俯いてカートを押した。
次第に落ちてゆく筋力。
心までが筋力を失い、地べたへ落ちてゆくようだった。
「まあ、ひさしぶり。覚えとる?」
整形外科の待合ベンチの私の横に、よろよろと腰を下ろした女性が不意に声をかけた。
前回ひどい言葉を医師にぶつけた私は、どんな顔で診察室へ入れば良いのか悩んでいた。
白髪混じりのおかっぱ頭、地味な紺色シャツにグレーのズボン。年齢五十歳過ぎか。
「髪が白くなったから、わからんかな?私、販売の仕事をしていて、時々会ってたんよ」
あ、美容部員の方だと思い出した。
だが、容貌が明らかに異なる。以前、デパートの化粧品売り場に立っていた頃は、栗色のロングヘアを色々アレンジし、お化粧も濃く、体に沿った黒いスーツに高いヒールのパンプスを履き、雑誌モデルのようだった。
「仕事は、怪我がきっかけでやめたんよ」
私があまりにも彼女の髪を見ていたからか、「二十代から若白髪。美容部員だから綺麗にって染め続けて。でも馬鹿馬鹿しくなって」と、白髪混じりの頭を撫でながら続けた。
「店の階段から落ちて肋骨と足を折ってな、松葉杖で無理して白髪染めを買いに行く私に、夫が言ったんよ。髪と体とどちらが大切か」
彼女は、ふっと天井を見上げて呟いた。
「私な、神様に一つ一つ返しているんよ」
「返す?」と、私は首を傾げた。
「生まれてから、歩くこと、喋ること、見ること、感じること、たくさん神様から授かってきたよな。感謝と共に返してゆくんよ。歳を重ねて、体の能力や器官が失われると嘆くんじゃなくて、返しているって考えるようにしているんよ。本来の自分に戻るんだって」
戸惑うような表情を向ける私に、彼女は、「嫉み、妬く。悔しいけど、女偏よな。誰かと比較したり、取り戻せない過去に溜息ついたり。女性だからこそ、やめたんよ。私を生きる。怪我を機に新たな旅立ちをしたんよ」と、満面の笑顔で見つめ返してきた。
彼女はデパートで見てきた人工的な造形美より、内側から滲み出るゆったりと穏やかな美しさに包まれ神々しくも映った。心で叫ぶ。
「女偏の嫉妬から解放され私らしく生きたい。新たに旅立ちたい。医師に素直に謝ろう」
診察室から、私の名前を呼ぶ声がした。