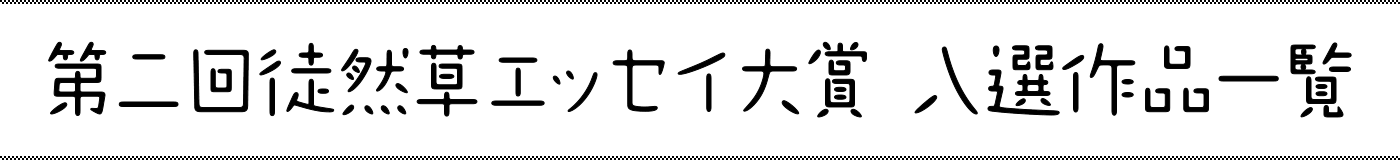
「ねぇ、お父さん、ゆげはどこへ行くの?」
「ゆげ?」
「ゆげはね、生まれてすぐ旅に出るでしょう、いったいどこへ行こうとしているの?」
小学一年生の娘が、うどんを前にして首をかしげている。
夏も終わりに近づいたころ、久しぶりに家族で外食をした。日々仕事に追われ、娘とゆっくり話をする時間もなかなか取れない私は、こんな時こそ父親としての役割を果たそうと、大いに意気込んで答えた。
「そもそもうどんの鉢から立ちのぼる湯気はだね、加熱された液体が気化して、それが水蒸気となり、比較的温度の低い空気中で冷えて凝結して、水滴となって白く見えているものなのだよ……」
娘の隣で、家内が冷たい視線を私に向けていたが、構わず続けた。
「しかも、地球上を取り巻く大気には圧力があって、それを気圧と呼ぶのだけれど、気圧の差によって空気を動かす力が生まれ、風となって吹くわけだ。したがって、あなたの目の前にあるうどんの湯気はだね……」
と、私がいよいよ興に乗り始めたところで、突然、娘が叫んだ。
「あっ、わかった!」
「な、何がだね?」
「スプーンの方に飛んでゆくんだよ!」
「スプーン?」
「ほら、スプーンがこっちに向いてるでしょ、だからこっちに行くんだよ!」
見れば、うどんの鉢に差し込まれたレンゲの柄の向く方角に、湯気は悠然と進んでいた。無論それは単なる偶然だ。科学的根拠などまるでない。本来このような暴論は断固否定されるべきだし、おまけにレンゲをスプーンと呼ぶのも少々気持ち悪い。しかし娘のあまりに無垢な発見に、私の心は動かされた。
娘は目の前で飛び去って行く湯気の行方に、科学の法則などではなく、一種の詩的、文学的、あるいは哲学的興味を抱いたのに違いない。ここで、かたくなに理詰めで押すのは無粋というものだ。むしろ今は、彼女とともに文学的世界に遊ぶのが父親としての役目だろう。
「本当だ!レンゲの柄のほうに、湯気は飛び立っているね!」
「でしょ。このスプーンが、あっちへ飛んで行けって教えているんだよ、きっと」
「じゃあ、このレンゲをこっちに向けたら、湯気はこっちに飛んでくるかもしれないね!」
私はレンゲの方向を変えてみた。果たして彼女の詩や文学は、どんな方向に飛んでゆくだろうか。
レンゲの方向転換に全く同調しない湯気を見つめながら、娘は「おかしいなぁ」と小さく呟いたきりだ。私は私で少々哲学的な方面に飛んでみた。
「ひょっとして、湯気は自分の思うままに旅をしたいんじゃないかな。湯気は自由が好きなんだよ、きっと」
そして、私は湯気の行く先に目をやりながら、ふと物思いに耽った。
思えば人生の旅路も、湯気のようなものかもしれない。人は皆、それぞれ思い思いの方向に、勝手気ままに進んで行くのだ。私自身も、両親や教師たちが示してくれた方向とは、全く違う道を歩んできたように思う。
果たしてそれが正しかったのかどうか、私には分らない。答えは全て風の中だ。
ここまで進んだ私の哲学的思索を、無残にもバッサリと切り捨てるように、またも娘が叫んだ。
「あっ、わかった!」
「えっ、な、何がだね?」
「エアコンだよ! エアコンの風の方向にゆげは流されているんだよ!」
こうして娘は科学的結論に帰着し、満足そうにうどんを食べ始めた。
「あぁ、ほんとだね……」
頭上の空調機から吐き出された微風は、私の力ない言葉も一緒に運び去って行った。
帰宅後、私は娘と風呂に入りながら、ぼんやりと考えた。
時の流れは速い。日々仕事に追われている間に、今は幼い娘も、あっという間に私の手元から飛び立って行くのだろう。果たして娘は、私の指し示す方向に従順に進んでくれるだろうか。それとも思いもよらぬ方向に行ってしまうのだろうか。
そんな私の不安をよそに、娘はただ無邪気にはしゃいでいる。
湯船から次々と立ちのぼる湯気は、細くあいた窓の隙間から、瞬く間に自由な外気へと旅立っていった。