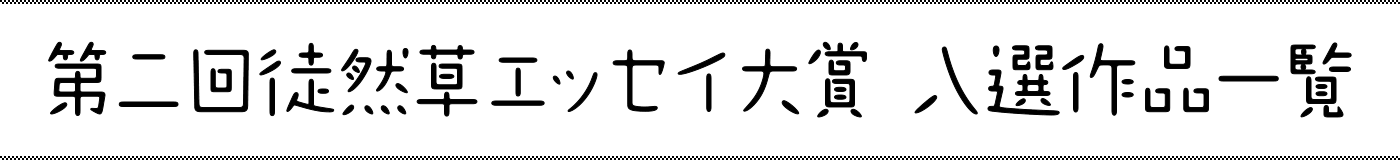
私が、初めて一年生を担任した時のことです。私のクラスにMくんという男の子がおりました。くりくり頭のかわいい子どもでした。
教師になって七年目の私は、研究することがおもしろく感じ始めた国語科教育、とりわけ作文教育にのめり込んでいました。
私は、受け持った子どもたちに、早く文を書いてほしいと思いました。それは、「楽しい作文を書かせたい」「一年生らしいおもしろい作文を書かせたい」という、まことに自分勝手で、子どもたちの実際を見ていない願望だったのです。
私は、四月の終わりには、さっそく文を書くことを教え始めました。
「習っていない文字は○で表してもよいから、自分の力で短い文を書いておいでなさい」 私は、子どもたちに日記を勧めました。
当時、大阪で実践を積んでおられた先達の、「一年生は文を書けないのではなく、先生方が書かさないから書けなくなるのです」ということばも、私の背中を強く押しました。
五月に入ってのある日のことです。
なかなか日記提出ができなかったMくんが、真新しいノートを手に、私の所におずおずとやってきました。
私はうれしくなって、Mくんの日記の第一ページを開きました。ところが、そのページは、ひらがなが数文字だけで、ほとんどが○で埋められていたのです。
私は、どきりとしました。思わず慎重になって、話す言葉を選びました。うれしそうに私を見つめる幼い目がそこにあります。
「Mくん。きみの口で、先生に読んで聞かせてくれへんか」私は、さりげなく言ったつもりでした。
けれど、M君は、ひと言もしゃべりませんでした。
たぶん、Mくんは、みんなが出している日記を自分だけが出していない、みんなと同じ事ができない悲しさを心に抱えていたのでしょう。だから、形だけでも出したという結果がほしかったのです。
それ以来、Mくんからの日記は出てこなくなりました。
そのことは、若い私に、文字とことばを教えることの難しさと子どもの先生に認められたいと願う一途な心の有り様を、突きつけたのです。
それでも、他の子どもたちからは、毎日短いながらも日記が提出されてきました。私は、それを学級通信に掲載し、みんなで読み合うことを続けました。
七月に入ると、子どもたちの日記もずいぶんことばが増え、手慣れたものに変わってきました。
そんな夏休み前のある日、Mくんの日記が突然、出されてきたのです。
「きのう、おかあさんとぎおんまつりにいきました。とてもうれしかったです」
「Mくんも、日記こそ提出できなかったけれど、ちゃんとひらがなを使えるようになっていたんだ」
私は、翌日の学級通信にMくんの日記を載せました。
夏休みに入り、家庭訪問でMくんのお家を訪ねた折には、私は躊躇せずMくんの日記の話を持ち出しました。
Mくんは、お母さんの背中に隠れて、肩越しにひょっこりと顔を出していました。
お母さんは、私の話を聞き終わると、少し顔を曇らせながら、お話を始められました。
「実は、この子も私も祇園祭に行っていないんです。学級通信を読んだ時、私は何でこんな嘘を書いたのかと、この子を叱ろうと思いました。けれど、よく考えてみると、この子もきっと他のお子さんと同じように祇園祭に行きたかったんだと、そう思えるようになりました。行きたいという思いが、この日記を書かせ、『いきました』という表現になったんじゃないでしょうか。そう思えるようになって、私はこの子に『よう書いたね』って言ってやることができました」
私は、お母さんのお話を聞きながら、改めて、小さな子どもの書いた文章を読むことの意味を考えさせられました。
形ばかりの良さを追い求める作文指導よりも、目の前にいる子どもの真実をとらえることができる作文指導を行わねばならない。子どもが書いたり話したりする拙いことばの裏側に存在する暮らしや思いを、読み取る教師にならなくてはならない。そう強く思ったのでした。
子どもの暮らしに寄り添い、子どもの心を育む大事さを教えられた夏の家庭訪問の一日。
その日から、三十五年余りの年月が過ぎました。しかし、今でも、その時のMくんのお母さんのきりっとした表情とMくんの笑顔を、くっきりと思い出すことがあります。