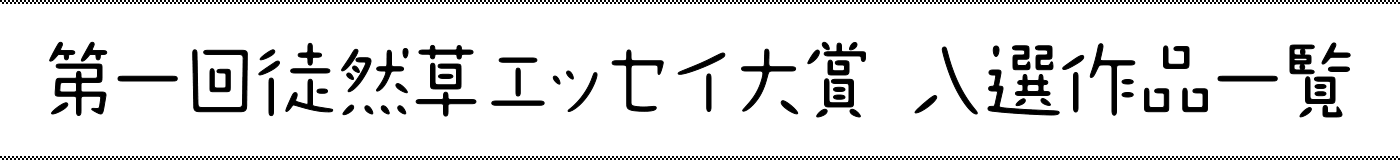
今から二十六年前に、私は
脳腫瘍を患った。約一ヶ月に渡る病院での闘病生活の記憶は、日を追うごとに薄れていった。
でも研修医のA先生と出会った時の感動は、今でもあの時と同じ温度でよみがえってくる。
私が三十二歳になったばかりの頃だった。その半年ほど前から、時々めまいを伴う頭痛と吐き気に襲われていたのだが、それが日増しにひどくなり、やがて目も見えにくくなってきた。
その年の夏、総合病院を受診したところ、MRIで頭の中に病巣があることが判明した。
入院して精密検査を受けた結果、下垂体腺腫という腫瘍で、鼻からアプローチする方法を勧められた。
入院してから、頭の手術をするという恐怖感よりも、女性として髪の毛をすべて剃ってしまわなければならないことへのショックの方が大きかった私は、思いもよらぬ朗報に心が躍った。
手術は無事成功し、その後の経過も順調で、鼻の中に詰めていたガーゼもようやく取れ、私は術後初めて自分の顔を鏡に映した。
その時の私が受けた衝撃は、今でも鮮明に覚えている。
手術前と比べて、大きくて平べったい鼻になり、顔を斜め横に向けてみると、鼻が幾分低くなったように思えた。
事前に医師から、鼻の骨を少し削るので、外見上、多少の変化は感じるかもしれないと説明を受け、頭の中では理解していたつもりだった。しかし、いざ、目の当たりに現実を突きつけられると、自分の感情を心に納めることが、どうしてもできなかった。
「この顔は自分じゃない。こんな顔なら私、いっそ死んでしまった方がよかったのに……」
自暴自棄になってしまった私は、ドクターや家族に八つ当たりした。
「今もまったく変わってないよ。以前の鼻がどんなだったかなんて、誰も覚えてないよ」
こんな周りの慰めは、余計に神経に障り、より苛立ちが募っていった。
「先生、形成外科を受診させてください。私の鼻を、元に戻してください」
回診時に、私は主治医に哀願した。彼は険しい眼差しで、ベッドの上の私を見下ろした。
「脳外科には、生きたくても生きられない患者さんがいっぱいいるんです。あなたはね、命が助かっただけでもラッキーなんですよ。あなたより鼻の低い人は、いっぱいいます!」
世の中の道理としては、優等生の回答だ……。私は言いようのない虚しさを感じた。
それから数日経ったある日のこと、時々主治医の後ろに控えていた研修医のA先生が、一人で病室に入ってきた。
彼女は私のベッドの横にしゃがみ込み、布団の上に顎をちょこんと置いて私の顔を見た。
彼女は、私と同じ目線になった。
「渡辺さんが気にされてるお鼻のことなんですけどね、私、同じ女性として、気持ちすごくわかります。もし私が渡辺さんだったら、たぶん同じように思っただろうなって。
これは私の提案なのですが、今から一年間という期限を設けて、じっくり考えてみられたらいかがでしょうか。そして一年後、まだ気になるようでしたら、その時は私も、微力ながら応援させていただきます」
彼女の言葉は一瞬にして、私の魂をわしづかみにした。
私はダムが決壊したかのように、大粒の涙が溢れ出してきた。
不思議な気持ちだった。あの時の私は、鼻が元に戻るかもしれないという、期待や喜びの感情よりも、自分の今の心境を共有してくれた嬉しさの方が、はるかに大きかった。
私は今回の入院で、医者と患者の距離感を痛切に感じていた。
当然のことながら、ベッドに横たわっている患者の前で、医者は立ったまま話をする。
患者の方は常に、医者に見下ろされる格好になり、医者のことを高圧的に感じる患者がいるかもしれない。体力、気力が弱っている時は尚更だということを、私は身をもって体験した。
A先生は、それをわかっていたのだろうか。彼女が掛けてくれた言葉は、退院後の私の心の拠り所となっていた。
いつしか私は、鏡を見ることも苦痛でなくなり、私の命を救ってくれた主治医に感謝の気持ちも芽生えてきた。
そして一年が経過したが、もしも今の顔にメスを入れたら、せっかく神様から授かった強運まで逃げて行ってしまいそうな気がして、この鼻とずっと付き合っていくことに決めた。
あの時、私の目線まで降りてきてくれたA先生に出会わなければ、今の私はない。
あれから長い歳月が経ち、A先生も今ではベテランのドクターになっているだろう。
今もどこかの病院で、患者さんのベッドに顎を乗せて話をしているだろうか。