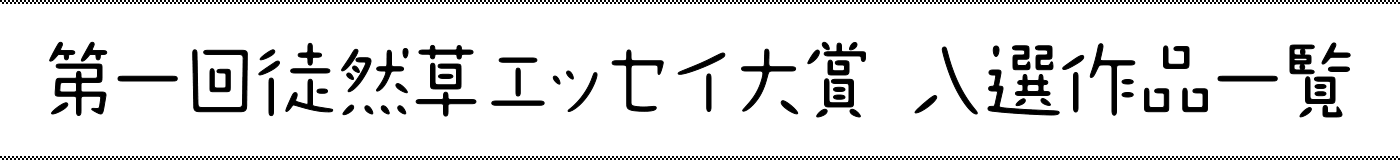
去年、私はもう一人の私と出会った。
数年前からなぜか体調を崩しやすくなり、少し運動しただけで動悸、息切れを起こすようになった。しかし特に生活に支障もなく、疲れか何かだろうとあまり深刻にとらえず放置していた。五月の連休明けに健康診断で病院に行くことがなければ、私は余命宣告を受けていたらしい。
健康診断にしては長い診察のあと別室に呼び出された私に向かって、すぐに大病院への紹介状を書きますからね、詳しいことはその病院でね、と早口で医師が告げた。隣の看護師が気の毒そうに小さな声で「がんばんなさいよ」と言ったことを覚えている。
悪性リンパ腫ステージⅢ。いわゆる血液のがんだった。肺と肺の間、縦隔という場所から発生した腫瘍が胸いっぱいに広がり、心臓や肺を圧迫していた。
病気の発症原因は今の医学では特定できていないんです、と大病院の主治医が言った。続けて、がん細胞は細胞のミスコピーなんです。だから誰の体の中にもあるし、もともと自分の細胞なんですよ、とも言った。
宣告から数週間、泣いたり喚いたり人生に絶望したりしながら、私は少しずつ現実を受け入れていった。しかし私の中には同時に、「今までの自分」と「がん患者の自分」が同居するようになった。
治療計画は早々に立てられた。抗がん剤と放射線治療、そして骨髄移植。一年半にわたる治療の副作用で髪は抜け、手足は痺れ、激しい吐き気に苦しんだ。家族、友人、恋人が見舞いに来て、頑張ってね応援しているからねと励ましの言葉をかけてくる。
簡単に頑張れと言われても困る。生きるための治療が、死ぬほどに辛いのだ。
貴方なら乗り越えられる、と私の手を取って励ましてくれる人がいた。ありがとうと笑顔で返事をした次の瞬間には、貴方に私の気持ちがわかるもんかと叫んで手を振り払いたい衝動に駆られた。貴方がどんな姿になっても私たちの関係は何も変わらないよ、という親友の言葉に涙を流して感謝しながら、同時にそんな薄っぺらい言葉今は聞きたくない、とひどい言葉が喉まで出かかったのを必死で飲み込んだ。
自分を支えてくれる周囲の人の愛情を素直に受け入れる自分とは別に、周囲すべての人に嫉妬して心を閉ざす、汚くてどろどろした嫌な自分がいるみたいだった。自分の中にこんな醜い部分があったことに驚いた。闘病の日々はがんと同時に、この嫌な自分と向き合い戦う日々でもあった。
転機となったのは、私の骨髄移植の日程が決定した日の夜だった。薄暗い病室で点滴に繋がれながら、痛い苦しい、なんで私ばっかりこんな目に、というもう一人の私の叫ぶ声を聞きながら、ただじっと白い天井を見上げていた。
遠慮がちにカシャ、とカーテンを開ける音がした。父だった。あまり眠れていないようで顔色が悪かった。少し痩せたようだった。
父は私を見て、次に私の腕に繋がる点滴を見て、ぐっと息を詰まらせた。そしてぽつりと「可哀想になあ。お前、痛いの嫌いだもんなあ。なんでお前がこんな目に。父さん、代われるものなら代わってやりたいよ」
その瞬間もう一人の自分の嘆く声がぴたりと止んだ。本当に自分でも不思議なくらい、ふっと気持ちが楽になった。
決して表に出すことはなかった、醜い嫌なもう一人の自分の本音。隠していたつもりだったのに、本当に身近な人にはばれていたのだ。私はその日、初めて父の前で泣いた。人目も憚らずに自分がいかに苦しいか、健康でキレイなままの同年代の友人がいかに妬ましいか、そんな風に考えてしまう今の自分がどれほど嫌らしく醜く感じるか。他にも色々なことを喚いた気がするが、あまり思い出せない。その日は泣き疲れてそのまま眠ってしまった。
そうして、私は少しずつ落ち着きを取り戻していった。治療は相変わらず辛く、一日中吐き気と戦う日もあったし、骨髄移植後は高熱で生死の境を彷徨ったこともあった。それでも心の健康だけは損なわずに済んだ。
見舞客が途切れることはなかった。術後安定してくると、少しずつ食事を摂れるようになった。無菌室の窓からは遠くに海が見えて、天気の良い日は日光が反射して海面がキラキラ光って、私はとても気分が良くなった。
無事治療を乗り切り退院してからも、鏡に映る自分の姿を見て、時々もうひとりの私が毒づくことはある。抜けた髪はまだ伸び始めたばかりだし、肌は治療の影響で所々黒ずみができている。それでも、病気になる前より人生がずっと愛おしく感じるし、他人を羨む醜い自分の部分も含めて、今の私の方がずっと好きだ。