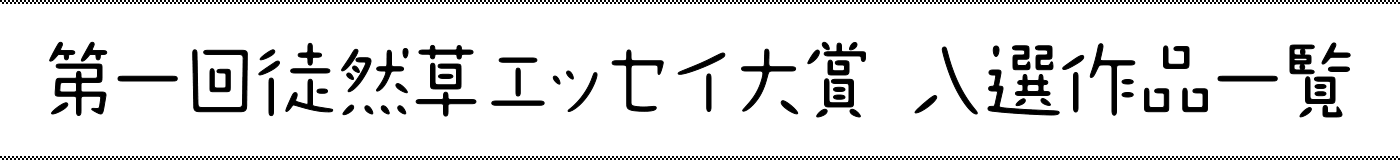
「悪魔」との馴れ初めは幼稚園の頃である。それまでは、私の幼い好奇心の芽を見守り育ててくれる通園路を、母と手を繋いで歩くのが大好きだった。しかし芽吹きの季節はいつしか過ぎる。雷のごとくに私の前に現れたのは、一匹の芋虫であった。
春の友達タンポポ、名を知らない植物の平行脈、沈黙する苔。私の記憶に足元の映像が多いのは、まだ背丈が低かったからだろう。わざとらしく黄色い五枚の花びら、吹いて遊ぶための綿毛、スミレ。この紫にはずっとどこか違和感があった。道端に咲くには高尚すぎる、だからといって花壇に植えるにはうら寂しい。しかしなるほど、悪魔の住処にはふさわしいような気がする。そいつはスミレの葉を好物とした。今思うと、葉の裏に隠れるとは姑息だ。驚いてしまうではないか。泣いてしまうではないか。
血のような赤い筋が、これまた血の酸化したような黒い体に走り、そこから立体的にほとばしったような棘。
それはまるで悪魔のような形相。恐怖のままに見ればそんな印象である。そいつを見つけた日の夜、ほの暗いオレンジの照明の下、隣の布団にいる母とこんな会話をしたことを覚えている。
「明日、幼稚園に行きたくない」
「どうして?」
「あの虫がいるから」
母は笑い、目でも瞑ればいいとか、気にするほどでもない、というようなことを言った。されど私にとっては本当に大事件だったのだ。小さい頭の中はそのことでいっぱいだった。
翌日、外は雨が降っていた。経験則で、雨の日に虫はどこか人目のつかないところに引き籠ってしまうのを知っていた。普段は憂鬱な降水にも感謝せざるを得なかった。あわよくば側溝で流されることを願いつつ、幼稚園へ向かった。
スミレをちらと見た。葉の陰はひっそりとして、何者の気配もない。ほっとして、進むべき道へと目線を動かす。すると、なんと、あの赤と黒の柔らかそうな体が、目の前で、ぺちゃんこに潰れていたのだ。世界中に向かって威嚇するような棘は見る形もない。母は、車に轢かれたのだと言った。気持ち悪いと心が拒絶する一方、そのグロテスクさにかえって目が離せなかったのも事実だ。おかげでまたその日の夜もそいつに悩まされた。目を瞑るとあまりにもはっきりと無残な姿が思い起こされたのは、瞼の裏にそれがへばりついていたからではなかったか。
その後、どのくらい経った後か思いだせないが、休日に虫好きの兄を連れてその悪魔をじっくり見に行こうということになった。私は最後まで抵抗したが虚しく、こわごわとついていった。三人で歩く休日の通園路はどこか特別な感じがした。どうか悪魔も休日であってほしかった。しかしその思いも虚しく、いつもの場に居座っていた。
「これはツマグロヒョウモンだ」
兄がそう言って、葉に手を伸ばしたのでぎょっとした。
「毒はないから」
指で摘み、掌に載せた。ツマグロヒョウモンは居心地が悪そうに身をよじる。
「近くで見てみな」
私は確かに恐れていたはずなのに、その時素直に顔を近づけたのは、通園路が育んでくれた好奇心の賜物だろう。そこにはちゃんと顔がついているし、私と同じように口がついていた。それなのにどこか不完全で、重い体を持て余すその姿に私は、
「意外と可愛い」
と呟いた。母も兄も笑っていた。
それからどんな経緯で飼うようになったかは記憶にない。ただそのうちに、腕や首に這わせるにも一切抵抗が無くなり、手に糞をされても所詮スミレ団子だと許せ、友達に気味悪がられるのと引き換えに通学路で見つけ次第捕まえるようになっていた。今までに飼育は数十回経験している。カマキリやカブトムシの成虫もよくケースに入れて飼っていたが、幼虫の飼育というのは羽化した瞬間が非常に印象的なのだ。蛹から目を離したすきに羽化していることがほとんどだが、一度だけ、その瞬間を見たことがある。
蛹化したツマグロヒョウモンは、部屋の壁に両面テープでくっつけて様子を見る。蛹になったからといって羽化に成功するとは限らず、気づいたらそのまま黒く変色してしまっていることもある。だから、蛹になるとなんだか気が気でなく、どうしようもないまま何度も蛹に目をやっていた。何十回目なのか、ちらっと視線を向けた時、上端のあたりが突然もぞもぞっと動いた。固いはずの蛹がゴムのようにぐにゃんぐにゃんと蠢き、三秒ほどして一気に割れた。その刹那、オレンジの光が殻から漏れ出たように思えた。その濡れた羽根が呼吸に合わせて揺れることの美しさ。蛹の残滓を振り切り、弱々しく飛び立つ。窓から放てば、風に吹かれたり逆らったりしながらどこかに消えていった。
毎回、羽化した蝶を見送る度に、幼虫のとき見た世界とどんなに違うことだろうと思いを馳せずにはいられない。そういえば、しばらくあの通園路を歩いていない。小さい頃より目線が高くなったから、また別の美しいものと私を出会わせてくれることだろう。